空き家どうする?売却・賃貸・解体・リフォーム|費用、補助金、税金、手続き完全ガイド
はじめに:深刻化する日本の空き家問題と所有者の課題

日本全国で空き家が増え続けており、社会的な問題としてその深刻さを増しています。所有者にとっては、固定資産税の負担、管理の手間、そして何よりも「この先どうすれば良いのか」という漠然とした不安が重くのしかかっているのではないでしょうか。本ガイドは、そのような空き家を所有する皆様が、ご自身の状況や空き家の状態に合わせて最適な選択肢を見つけられるよう、具体的な情報を提供することを目的としています。
空き家の現状:統計データと背景
総務省が2024年9月25日に公表した2023年の住宅・土地統計調査(確定版)によると、日本の総住宅数、空き家数ともに過去最多を記録しました。空き家数は900万戸に達し、空き家率も13.8%と過去最高を更新しています 。これは、5年前の2018年の調査(849万戸、空き家率13.6%)と比較して、空き家数が51万戸増加し、空き家率も0.2ポイント上昇したことを意味します 。特に、これまで比較的空き家問題が深刻ではなかった都市圏においても空き家率が上昇している点は、問題の広がりを示唆しています 。
空き家の中でも特に問題視されるのが、「その他の空き家」と呼ばれる、賃貸用でも売却用でもなく、別荘などの二次的利用もされていない、つまり利用目的のない空き家です。この「その他の空き家」は2023年には385万戸に達し、2018年と比較して37万戸も増加しています 。国土交通省の資料によれば、この種の空き家は過去20年間で約1.9倍に増加しており 、放置されるリスクが高い空き家が急速に増えている現状が浮き彫りになります。
空き家を取得した経緯を見ると、「相続」が約55%と半数以上を占めているというデータがあります 。さらに、空き家の所有者の約3割は、その物件から車や電車で1時間以上かかる遠隔地に居住しており、また、所有世帯の家計を支える者の約6割以上が65歳以上の高齢者であるという実態も明らかになっています 。これらのデータは、多くの方が予期せぬ形で、あるいは準備が整わないまま空き家を所有することになり、地理的な距離や年齢的な要因から、適切な管理や活用が難しい状況に置かれやすいことを示しています。このような「意図せざる所有者」が直面する負担感や戸惑いを軽減するためにも、分かりやすく実践的な情報提供の必要性が高まっています。
なぜ空き家対策が必要なのか?放置するリスクと新法の影響
空き家を放置することは、所有者自身だけでなく、周辺環境にも多大なリスクをもたらします。老朽化による倒壊の危険性、ゴミの不法投棄や害虫発生による衛生環境の悪化、雑草の繁茂や建物の破損による景観の阻害、さらには不審者の侵入や放火といった防犯上の問題も懸念されます 。
こうした状況に対応するため、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家法)が、2023年12月に改正・施行されました。この改正の大きなポイントの一つは、従来の「特定空家」に至る前の段階である「管理不全空家」という区分が新たに設けられたことです 。これにより、行政はより早期の段階で空き家の所有者に対して指導や勧告を行うことが可能となり、所有者の管理責任が一層明確化されました。
この法改正は、国や自治体が空き家問題に対して、単なる推奨や呼びかけに留まらず、より積極的な介入と対策強化へと舵を切ったことを意味します。例えば、緊急時には行政代執行による解体も迅速に行えるようになるなど 、所有者が問題を先送りできる余地は狭まりつつあります。また、改正法では、空き家所有者に対して国や自治体の施策に協力する努力義務も加えられており 、受け身の姿勢ではいられない状況が生まれています。
本ガイドの目的と構成
このガイドは、空き家を所有する皆様が、ご自身の状況や空き家の状態に合わせて最適な選択肢(売却・賃貸・解体・リフォーム)を検討できるよう、各選択肢の費用、補助金、税金、手続きについて網羅的に解説することを目的としています。空き家問題という複雑な課題に対し、具体的な情報と道筋を示すことで、皆様の不安を少しでも解消し、より良い未来への一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
あなたの空き家、まずは現状把握から
空き家対策を検討する上で、最初に行うべきことは、所有する空き家の現状を正確に把握することです。特に、放置によってどのような状態と判断され、どのような措置が取られる可能性があるのかを理解しておくことは非常に重要です。

放置が招く「特定空家」「管理不全空家」とは?
空き家を適切に管理せずに放置すると、行政から「管理不全空家」や「特定空家」に指定される可能性があります。これらの指定を受けると、税制上の不利益や行政措置の対象となるため、注意が必要です。
管理不全空家 とは、そのまま放置すれば「特定空家」に該当するおそれのある状態の空き家を指します 。国土交通省が示すガイドラインでは、具体的な状態として、建物の構造部材の破損や腐朽、窓ガラスの破損、敷地内の雑草の繁茂、門や塀の小規模な破損などが例示されています 。
市町村長は、管理不全空家の所有者に対し、必要な措置をとるよう指導することができます。指導に従わず状況が改善されない場合、勧告が出されることがあります 。この勧告を受けると、固定資産税及び都市計画税の「住宅用地の特例」が解除され、税負担が大幅に増加する可能性があります 。これは、後述する「特定空家」に対する勧告と同様の措置であり、早期の対応が求められます。
特定空家 とは、以下のいずれかの状態にあると認められる空き家です 。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(例:建物の著しい傾斜、基礎の沈下、屋根や外壁の広範囲な脱落)
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態(例:ゴミの放置による害虫・害獣の繁殖、汚物の異臭)
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(例:多数の窓ガラスの破損、落書き、立木の著しい繁茂、既存の景観ルールとの著しい不適合)
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(例:立木の枝の越境による通行障害、動物の鳴き声や糞尿の臭気、不審者の侵入の容易さ)
特定空家に認定されると、行政は所有者に対して助言・指導、勧告、命令といった段階的な措置を行います。命令に従わない場合は50万円以下の過料が科される可能性があり、最終的には行政代執行(強制的な解体など)が行われることもあります 。
「管理不全空家」や「特定空家」の認定基準は、「景観を損なっている状態」や「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」といった、ある程度幅広く解釈できる文言も含まれています 。これは、自治体によって判断に差異が生じる可能性を示唆しており、所有者自身が「まだ大丈夫だろう」と考えていても、突然指導の対象となるケースも考えられます。そのため、単に建物が構造的に安全であるだけでなく、外観の維持管理や敷地内の清掃など、周囲への配慮を含めた積極的かつ目に見える形での管理が重要となります。
1: 「管理不全空家」と「特定空家」の比較
| 項目 | 管理不全空家 | 特定空家 |
| 定義 | そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等 | 保安上危険、衛生上有害、景観阻害、その他周辺の生活環境の保全に不適切な状態にある空家等 |
| 主な認定基準の例 | ・構造部材の破損・腐朽等 ・門、塀等の破損・腐朽等 ・立木の腐朽 ・擁壁のひび割れ、水のしみ出し等 ・外装材等の破損、支持部材の腐食等 | ・建物の著しい傾斜、倒壊の危険 ・ゴミ放置による害虫・悪臭 ・窓ガラスの多数破損、落書き、立木の著しい繁茂 ・不審者の侵入容易性、動物の糞尿被害等 |
| 主な行政措置 | 指導、勧告 | 助言・指導、勧告、命令(違反時過料)、行政代執行 |
| 税制上の措置 | 勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例が解除 | 勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例が解除 |
この表は、「管理不全空家」と「特定空家」の違い、リスクの段階、そしてそれぞれに対する行政の対応を明確に示しています。特に、税制上の措置はどちらの段階の勧告でも同様に厳しいため、「管理不全空家」の段階で迅速に対処することの重要性がわかります。
意思決定の前に:確認すべきポイント
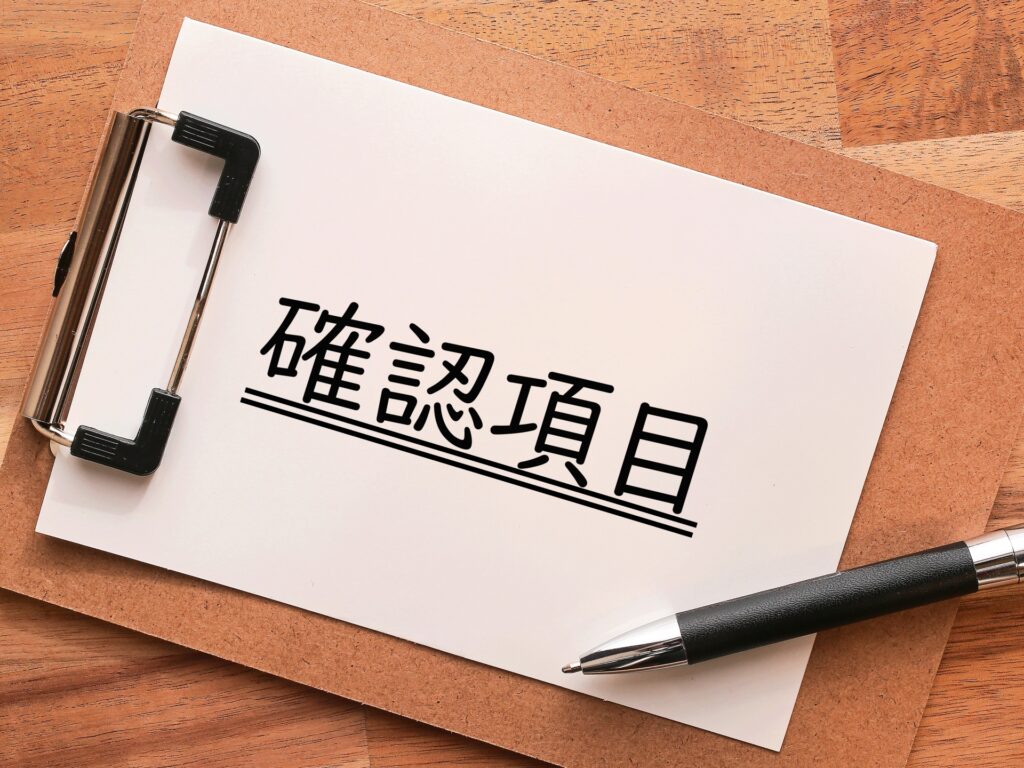
空き家をどうするかという最終的な意思決定を下す前に、以下の点をしっかりと確認・整理しておくことが不可欠です。
- 物件の権利関係:
- 登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、現在の名義人を確認します。相続した場合は、相続登記が完了しているか確認が必要です。
- 抵当権や差押えなどの権利が設定されていないか確認します。
- 建物の状態:
- 建築年、構造(木造、鉄骨造など)、延床面積。
- 老朽化の程度(雨漏り、シロアリ被害、基礎の状態など)。専門家による建物診断(ホームインスペクション)も有効です。
- 耐震性(特に昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物か、それ以降の新耐震基準の建物か)。
- 立地条件:
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの法規制。
- 周辺環境(商業施設、学校、病院、公園など)。
- 交通アクセス(最寄り駅からの距離、バス便の有無、道路付け)。
- 賃貸や売却の際の需要が見込めるエリアか。
- 関連法規:
- 都市計画法、建築基準法、消防法など、物件に関わる法規制を確認します。再建築の可否なども重要です。
- 自身の意向と経済状況:
- 将来的に自己利用(居住、事業用など)する可能性はあるか。
- 売却、賃貸、解体、リフォームの各選択肢にかけられる予算はどの程度か。
- 維持管理にどの程度の時間と労力を割けるか。
これらの情報を総合的に検討することで、より現実的で後悔のない選択が可能になります。
選択肢①:空き家を「売却」する

空き家を手放す最も直接的な方法の一つが「売却」です。維持管理の負担や将来的な不安から解放される一方で、いくつかの注意点も存在します。
売却のメリット・デメリット
メリット:
- 維持管理コストからの解放: 固定資産税や都市計画税、火災保険料、定期的な修繕費といった継続的な支出がなくなります。
- 現金化: 売却代金を得ることで、他の資産形成やローンの返済などに充てることができます。
- 管理の手間からの解放: 草むしりや換気、防犯対策といった物理的な管理業務から解放されます。
- 精神的な負担の軽減: 空き家を所有し続けることによる将来への不安や、近隣への配慮といった精神的なプレッシャーが軽減されます。
デメリット:
- 希望価格で売れない可能性: 物件の状態や立地、市場の状況によっては、期待した価格で売却できないことがあります。
- 思い出の詰まった家を手放す寂しさ: 特に相続した実家などの場合、愛着のある家を手放すことに対する精神的な抵抗感が生じることがあります。
- 売却益に対する税金: 売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税が課税されます。
- 諸経費の発生: 仲介手数料や印紙税など、売却に伴う費用が発生します。
売却プロセスと主な手順
空き家の売却は、一般的に以下の流れで進められます 。
- 不動産会社の選定と査定依頼:
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、査定価格だけでなく、販売戦略や担当者の対応などを比較検討します 。
- 媒介契約の締結:
- 売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。契約形態には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
- 売却活動の開始:
- 不動産会社が物件情報を不動産流通機構(レインズ)に登録したり、自社のウェブサイトやチラシなどで広告宣伝活動を行います 。売主は内覧希望者への対応などを行います。
- 購入希望者との条件交渉:
- 購入希望者が見つかると、価格や引き渡し時期などの条件交渉を行います。交渉は不動産会社が間に入って進めるのが一般的です。
- 売買契約の締結:
- 条件が合意に至れば、売買契約を締結します。この際、買主から手付金(物件価格の5~10%程度)を受領します 。
- 決済・物件の引き渡し:
- 契約で定めた引き渡し日に、買主から残代金を受領し、物件の鍵などを引き渡します。同時に所有権移転登記の手続きも行われます 。
- 確定申告:
- 売却によって譲渡所得が生じた場合は、翌年に確定申告が必要です 。
売却を進める上での注意点として、まず、相続した空き家を売却する場合、売却前に相続登記を済ませ、名義を現在の所有者に変更しておく必要があります 。また、売却前にリフォームや解体を行うべきか悩むケースがありますが、費用をかけても必ずしも売却価格が上がったり、売れやすくなったりするとは限らないため、不動産会社とよく相談することが重要です 。
売却にかかる費用(仲介手数料、印紙税など)
空き家を売却する際には、様々な費用が発生します。主なものは以下の通りです。
- 仲介手数料: 不動産会社に支払う成功報酬です。売買契約が成立した場合にのみ発生します。宅地建物取引業法により上限額が定められています。
- 売買価格が400万円を超える場合:(売買価格×3%+6万円)+消費税。
- 低廉な空き家等の売買・交換の媒介における特例:売買価格が800万円以下の物件で、通常の仲介手数料では調査費用等を賄いきれない場合など、特例として依頼者(売主)から受け取れる仲介手数料の上限が30万円(税抜)となる場合があります 。
- 印紙税: 不動産売買契約書に貼付する収入印紙の代金です。契約金額によって税額が異なります 。
- 例:契約金額が500万円超1,000万円以下の場合、本則税率は1万円ですが、軽減措置により現在は5,000円となっています(令和9年3月31日まで) 。
- 抵当権抹消登記費用: 売却する物件に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合に、それを抹消するための手続き費用です。
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円(土地と建物であれば2,000円) 。
- 司法書士報酬:司法書士に手続きを依頼する場合に支払う報酬で、一般的に1万円~3万円程度です 。
- その他の費用:
- 譲渡所得税・住民税: 売却益が出た場合に課税されます(詳細は後述)。
- 建物解体費用: 古家付き土地としてではなく、更地として売却する場合に必要です 。
- 測量費用: 隣地との境界が未確定な場合や、土地の一部を売却する場合などに必要となることがあります。
- 遺品整理・ハウスクリーニング費用: 家の中に家財道具が多く残っている場合や、清掃が必要な場合に発生します。
2: 空き家売却時の主な諸費用
| 費用項目 | 内容・計算方法(例を交えて) | 目安金額 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬。売買価格400万円超の場合「(売買価格×3%+6万円)+消費税」。例:1,000万円で売却時、39.6万円(税込) 。低廉な空き家特例あり。 | 売却価格により変動 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付。契約金額により変動。例:500万円超1,000万円以下で5,000円(軽減税率適用時) 。 | 数千円~数万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 抵当権がある場合。登録免許税(不動産1個につき1,000円)+司法書士報酬(1~3万円程度) 。 | 約1.2万円~3.2万円(不動産2個の場合) |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益(譲渡所得)が出た場合に課税。譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)。税率は所有期間による。 | 譲渡所得や所有期間により大きく変動 |
| その他 | ・建物解体費(更地にする場合) ・測量費(境界未確定等の場合) ・遺品整理費、ハウスクリーニング費 ・アスベスト調査費用(解体時等) | 必要に応じて数十万円~数百万円 |
この表は、売却時にかかる可能性のある主な費用をまとめたものです。これらの費用を事前に把握しておくことで、手取り額を予測し、資金計画を立てる上で役立ちます。
売却に関する税金(譲渡所得税、3,000万円特別控除など)
空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得税・住民税 譲渡所得は以下の計算式で算出されます 。
譲渡所得=売買価格-(取得費+譲渡費用)
- 取得費: 売却した不動産の購入代金や購入時にかかった諸費用(仲介手数料、登記費用など)です。相続した物件で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することができますが、実際の取得費が分かっている場合に比べて譲渡所得が大きくなり、税負担が増える可能性があります 。
- 譲渡費用: 不動産の売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、解体費用など)です。
税率は、不動産の所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率が大きく変わります。
- 短期譲渡所得の税率:所得税30.63% + 住民税9% = 39.63%
- 長期譲渡所得の税率:所得税15.315% + 住民税5% = 20.315% (では短期譲渡所得の税率を約40%と記載、長期譲渡所得の具体例で20.315%が示されています)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(3,000万円特別控除) 相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(空き家)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例制度があります 。この特例を適用できれば、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
主な適用要件は以下の通りです 。
- 対象家屋:
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
- 区分所有建物登記がされていない家屋であること。
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合などの例外規定あり)。
- 相続・売却のタイミング:
- 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- この特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること 。
- 売却価格: 売却代金が1億円以下であること。
- 家屋の状況:
- 相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、または居住用として使用されていないこと。
- 売却する家屋が一定の耐震基準を満たすものであるか、または家屋を解体して土地のみを売却する場合。
- 令和6年1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合や、買主が建物を解体した場合でも、一定の条件を満たせば特例の対象となるように拡充されました 。
- その他:
- 親子や夫婦など特別な関係がある人への売却ではないこと。
- 過去に同一の被相続人から相続した空き家について、この特例の適用を受けていないこと。
この特例を受けるためには、確定申告の際に、市区町村から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」などの必要書類を税務署に提出する必要があります 。
この3,000万円特別控除は非常に節税効果が高い制度ですが、適用要件が細かく定められています。特に、建物の建築時期や被相続人の居住実態、相続後の物件の使用状況、売却のタイミングなどが厳格に問われます。また、取得費の証明書類の有無は、そもそも譲渡所得の計算に大きく影響します。相続が発生した際には、これらの税務上の特例を念頭に置き、必要な書類(建築確認済証、売買契約書、領収書など)を早期に確認・収集し、売却までのスケジュールを計画的に進めることが、経済的なメリットを最大限に享受する上で極めて重要です。知識不足や準備不足から、大きな節税機会を逃したり、想定外の税負担を強いられたりするケースも少なくありません。
売却を成功させるためのヒント

空き家をより有利な条件で、スムーズに売却するためには、いくつかのポイントがあります。
- 適切な価格設定: 周辺の類似物件の売出価格や成約価格といった相場を事前に調べておくことが重要です 。不動産会社の査定価格を鵜呑みにせず、自身でも情報を集め、納得のいく価格で売り出すことが大切です。
- 物件の魅力を高める:
- 清掃・整理整頓: 内覧時の第一印象は非常に重要です。室内や庭の手入れをしっかり行いましょう。不要な家財道具は処分し、スッキリとした状態にしておくことが望ましいです。
- 軽微な修繕: 壁紙の汚れや小さな破損など、低コストで修繕できる箇所は対応しておくと、印象が良くなることがあります。
- ホームステージング: 家具や小物を配置して、モデルルームのように生活空間を演出し、物件の魅力を高める手法も有効です。
- 信頼できる不動産会社を選ぶ:
- 査定価格の高さだけでなく、販売実績、地域への精通度、担当者の熱意や提案力などを総合的に判断しましょう。
- 空き家の売却に特化したノウハウを持つ会社を選ぶのも一つの方法です。
- 内覧時の丁寧な対応: 購入希望者からの質問には誠実に答え、物件の良い点だけでなく、修繕が必要な箇所なども正直に伝えることで、信頼関係を築くことができます。
選択肢②:空き家を「賃貸」に出す

空き家をすぐに手放すのではなく、収益化を目指す方法として「賃貸」があります。安定した家賃収入が期待できる一方で、貸主としての責任やリスクも伴います。
賃貸のメリット・デメリット
メリット:
- 継続的な家賃収入: 入居者がいる限り、毎月安定した収入を得ることができます。
- 資産の維持・活用: 定期的な収入を得ながら、資産として持ち続けることができます。
- 将来的な自己利用の可能性: 将来、自分や家族が住むために空き家を残しておきたい場合に有効です。
- 適切な管理による資産価値の維持: 人が住むことで家の傷みが遅れ、定期的なメンテナンスが行われることで資産価値を保ちやすくなります。
- 節税効果: 賃貸経営にかかる費用(固定資産税、修繕費、減価償却費など)を経費として計上できるため、所得税や住民税の節税につながる場合があります。
デメリット:
- 空室リスク: 常に入居者がいるとは限らず、空室期間は家賃収入が得られません。
- 家賃滞納リスク: 入居者が家賃を滞納する可能性があります。
- 入居者トラブルのリスク: 騒音問題やゴミ出しルール違反など、入居者間のトラブルや近隣とのトラブルが発生する可能性があります。
- 修繕費用の発生: 給湯器の故障や雨漏りなど、建物の維持管理や設備の修繕・交換に費用がかかります。
- 管理の手間: 入居者募集、契約手続き、家賃集金、クレーム対応、退去時の立ち会いなど、貸主としての業務が発生します。
- 建物の老朽化: 経年劣化は避けられず、将来的には大規模修繕が必要になることもあります。
- 売却の制約: 入居者がいる状態では、自己都合での売却や立ち退きが難しくなる場合があります。
賃貸プロセスと主な手順(入居者募集、管理委託)
空き家を賃貸に出す際の一般的な流れは以下の通りです 。
- 賃貸管理会社の選定と賃料査定依頼:
- 複数の不動産会社(賃貸管理会社)に相談し、周辺の家賃相場や物件の状態に基づいた賃料査定を依頼します。
- 管理委託契約の締結(または自主管理の準備):
- 入居者募集から家賃集金、トラブル対応、退去手続きまで一括して委託する場合は、管理委託契約を締結します。手数料は家賃の5%程度が一般的です。
- 自主管理も可能ですが、専門知識や時間、手間がかかるため、特に遠方に住んでいる場合や賃貸経営が初めての場合は、管理会社への委託を検討するのが賢明です。
- 入居条件・家賃の設定:
- ターゲットとする入居者層(単身者、ファミリーなど)を想定し、家賃、敷金、礼金、契約期間などの入居条件を決定します。
- 入居者募集:
- 管理会社を通じて、不動産情報サイトへの掲載や店頭での広告など、入居者募集活動が行われます。必要に応じて、リフォームやハウスクリーニングを実施します。
- 入居審査:
- 入居希望者から申込があった場合、支払い能力や連帯保証人の有無などを審査します。最終的な入居可否は貸主が判断します 。
- 賃貸借契約の締結:
- 入居者と賃貸借契約を締結します。契約書の内容をしっかり確認することが重要です。
- 入居後の管理:
- 家賃集金、入居者からの要望やクレームへの対応、建物の維持管理(定期点検、修繕手配など)を行います。
- 確定申告:
- 賃貸経営で得た所得(不動産所得)は、毎年確定申告が必要です。
賃貸経営は、単に物件を貸して家賃収入を得るだけでなく、入居者対応や建物の維持管理、税務処理など、多岐にわたる業務が伴います。特に、空き家の所有者が遠方に住んでいる場合や、本業で多忙な場合、これらの業務をすべて自分で行うのは大きな負担となります。不動産所得の計算や確定申告も専門的な知識が必要となるため、不慣れな場合は税理士などの専門家のサポートも検討すると良いでしょう。
賃貸経営にかかる費用と収入(管理費、修繕積立金、家賃収入)
空き家を賃貸に出す際には、様々な費用が発生し、一方で家賃収入が得られます。
初期費用(貸主側負担):
- リフォーム・修繕費用: 賃貸に出せる状態にするために必要な内装工事、設備交換(キッチン、浴室、トイレなど)、ハウスクリーニング費用など。
- 鍵交換費用: 防犯上、入居者が変わるごとに鍵を交換するのが一般的です。
- 広告宣伝費: 入居者募集を不動産会社に依頼する際、広告料がかかる場合があります。
- なお、借主が契約時に支払う初期費用(敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、火災保険料、保証料など )は、貸主の収入(礼金など)になるものや、預かり金(敷金)、不動産会社への支払い(仲介手数料)など様々です。敷金は原則として退去時に原状回復費用を差し引いて返還するものです。
運営費用(経費として計上できるもの): 賃貸経営で得た収入から差し引くことができる経費には、以下のようなものがあります 。
- 管理委託手数料: 管理会社に管理を委託する場合に支払う手数料(通常、家賃収入の5%前後)。
- 修繕費: 給湯器の交換、エアコンの修理、壁紙の張り替え、共用部分の電球交換など、建物の維持管理や原状回復にかかる費用。ただし、建物の価値を高めるような工事(資本的支出)は、一度に経費計上できず減価償却の対象となる場合があります 。
- 固定資産税・都市計画税(租税公課): 土地と建物に対して毎年課税されます。
- 損害保険料: 火災保険や地震保険など、賃貸物件にかける保険料。
- 減価償却費: 建物や設備の取得費用を、法定耐用年数に応じて分割して経費計上するもの。土地は減価償却の対象外です。
- 借入金利息: 物件購入のためにローンを利用している場合、その支払利息部分。元本返済部分は経費になりません。
- 広告宣伝費: 新たな入居者を募集するために不動産会社に支払う手数料や広告掲載料。
- その他: 賃貸経営のために直接要した交通費(物件確認や管理会社との打ち合わせなど)、通信費、消耗品費、税理士報酬など。
4: 賃貸経営における主な経費
| 経費項目 | 内容説明 | 計上時の注意点 |
| 租税公課 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税など 。 | 所得税・住民税は経費にならない 。 |
| 損害保険料 | 賃貸物件にかける火災保険、地震保険など 。 | 複数年契約でも支払った年度に全額経費計上(期間按分ではない)。 |
| 減価償却費 | 建物や設備の取得費用を耐用年数で分割して計上 。 | 土地は対象外。耐用年数は構造により異なる 。 |
| 修繕費 | 原状回復や維持管理のための費用(壁紙張替、設備修理等)。 | 価値を高める工事(資本的支出)は減価償却。20万円以上の修繕は資本的支出の可能性あり 。 |
| 借入金利息 | 物件購入ローンの利息部分 。 | 元本返済部分は経費にならない 。 |
| 管理費 | 管理会社への委託手数料、共用部分の清掃費、点検費など 。 | |
| 広告宣伝費 | 入居者募集のための広告費、不動産会社への委託費 。 | |
| その他 | 交通費、通信費、司法書士・税理士報酬、消耗品費など、賃貸経営に直接必要なもの 。 | 私的利用との按分が必要な場合あり 。 |
この表は、賃貸経営における経費の概要を示しています。正確な経費計上は節税に繋がるため、領収書などをきちんと保管し、不明な点は専門家に相談することが重要です。
家賃収入: 設定した家賃から得られる収入です。空室期間や滞納がなければ、安定した収入源となります。
賃貸に関する税金(不動産所得税)
賃貸経営によって得られた所得は「不動産所得」として、所得税と住民税の課税対象となります。
不動産所得は以下の計算式で算出されます 。
不動産所得=総収入金額-必要経費
- 総収入金額: 家賃収入のほか、礼金、更新料、共益費などが含まれます 。敷金のうち、返還を要しない部分も収入となります。
- 必要経費: 前述の運営費用(管理委託手数料、修繕費、固定資産税、損害保険料、減価償却費など)です。
算出された不動産所得は、給与所得など他の所得と合算され(総合課税)、その合計額に対して所得税と住民税が課税されます 。所得税は累進課税制度が採用されており、所得が多いほど税率が高くなります 。
給与所得者であっても、不動産所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です 。逆に、不動産所得が赤字になった場合は、給与所得など他の黒字の所得と損益通算することで、納めすぎた税金が還付されることもあります 。
また、青色申告を選択し、一定の要件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができ、節税効果が期待できます 。青色申告を行うには、事前に税務署への届出が必要です。
「空き家バンク」の活用法
「空き家バンク」とは、主に地方自治体が主体となって運営している、空き家の情報を集約し、利用希望者とのマッチングを支援するシステムです 。
所有者側の利用の流れ(例):
- 登録申請: 自治体が指定する申込書や物件情報を提出して登録を申請します。
- 現地調査: 自治体の担当者や提携する宅建業者などが物件を調査し、登録の可否や掲載情報を確認します。
- 空き家バンクへの登録・情報公開: 調査後、問題がなければ物件情報が空き家バンクのウェブサイトなどに公開されます。
利用希望者側の利用の流れ(例):
- 利用登録: 多くの場合、事前に利用登録が必要です。登録しないと詳細情報が閲覧できないこともあります。
- 物件検索: 公開されている情報から希望に合う物件を探します。
- 現地確認: 気になる物件があれば、自治体を通じて見学を申し込みます。
- 交渉・契約: 購入や賃貸を希望する場合、自治体や提携宅建業者の仲介のもと、所有者と交渉し、契約に至ります。
メリット:
- 低コストでの情報発信: 自治体が運営しているため、民間の不動産ポータルサイトに比べて低コストで物件情報を掲載できる場合があります。
- 地域活性化への貢献: 空き家の活用を通じて、移住促進や地域の活性化に繋がる可能性があります。
- 公的な安心感: 自治体が関与することで、一定の安心感が得られる場合があります。
デメリット:
- 成約までに時間がかかる可能性: 利用希望者がすぐに見つかるとは限りません。
- 運営状況の地域差: 自治体によって空き家バンクの運営体制や活発さに差があります。
- 条件交渉の手間: 直接交渉に近い形になる場合、条件調整に手間がかかることがあります。
空き家バンクは、特に地方の物件や、通常の不動産市場では買い手や借り手が見つかりにくい物件にとって、有効な選択肢の一つとなり得ます。
選択肢③:空き家を「解体」する

老朽化が著しい空き家や、土地としての活用を優先したい場合、「解体」という選択肢が考えられます。危険性の除去や管理負担の軽減といったメリットがある一方、費用負担や税金の変動には注意が必要です。
解体のメリット・デメリット(固定資産税の変動など)
メリット:
- 倒壊・破損などの危険性除去: 老朽化した建物が倒壊したり、部材が飛散したりするリスクを根本的になくすことができます。これにより、近隣への迷惑や損害賠償責任のリスクを回避できます。
- 管理の手間の大幅な軽減: 建物の維持管理(清掃、修繕、防犯対策など)が不要になり、管理負担が大幅に減ります。
- 土地の売却や活用の選択肢が広がる: 更地にすることで、土地として売却しやすくなったり、駐車場や新規建築など、土地活用の自由度が高まります。
- 「特定空家」指定リスクの回避: 建物がなくなるため、「特定空家」や「管理不全空家」に指定される心配がなくなります。
デメリット:
- 解体費用の発生: 建物の構造や規模、立地条件によって高額な解体費用がかかります。
- 固定資産税・都市計画税の増額リスク: 建物を解体して更地にすると、土地に対する固定資産税や都市計画税の「住宅用地の特例」が適用されなくなります。これにより、土地の税額が大幅に上昇する可能性があります 。
- 住宅用地の特例とは: 住宅やアパートなどの敷地(住宅用地)については、課税標準額が軽減される特例措置です。具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税評価額の1/6に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は1/3に軽減されます。都市計画税についても、それぞれ1/3、2/3に軽減されます 。
- 建物を解体すると、この特例の対象外となるため、土地の固定資産税は最大で6倍、都市計画税は最大で3倍になる計算です。
- ただし、多くの自治体では税負担の急増を緩和するための負担調整措置が講じられているため、必ずしも理論上の上限まで税額が跳ね上がるとは限りません 。それでも、一般的には1倍から3倍程度の上昇が見込まれることが多いです。
- 思い出の喪失: 長年住んだ家や実家を解体することに対する寂しさや喪失感を感じることがあります。
建物を解体すれば固定資産税が安くなると思われがちですが、実際には土地にかかる税金が大幅に増える可能性があるという点は、非常に重要なポイントです。この「税金の逆転現象」を理解せずに解体を進めてしまうと、後で想定外の税負担に苦しむことになりかねません。したがって、解体は単に古い家をなくすという行為ではなく、その後の土地の利用計画(速やかな売却、新たな建築など)とセットで、税金面も含めた総合的な資金計画のもとで判断する必要があります。
5: 固定資産税・都市計画税:解体による影響シミュレーション(概念図)
| 状態 | 土地の固定資産税(計算根拠) | 建物の固定資産税 | 合計税額(概算イメージ) |
| 建物あり (住宅用地特例適用時) | 評価額 × 1/6 (小規模住宅用地の場合) × 税率 | 評価額 × 税率 | 低い |
| 建物解体後 (更地・特例解除時) | 評価額 × 1 (軽減なし) × 税率 | なし | 大幅に上昇する可能性あり |
| 注記:実際の税額は、土地・建物の評価額、面積、所在地(税率)、自治体の負担調整措置などによって大きく異なります。上記は特例の有無による変化のイメージです。 |
この表は、住宅用地の特例が適用される場合とされない場合で、土地の固定資産税の計算根拠がどう変わるかを示しています。建物がなくなることで建物分の税金はゼロになりますが、土地の税負担が増加するため、トータルでの税額変動を慎重に試算する必要があります。
解体プロセスと主な手順(アスベスト調査、滅失登記など)
建物の解体工事は、専門的な知識と許可が必要な作業であり、適切な手順を踏む必要があります。
- 解体業者の選定と見積もり依頼:
- 複数の解体業者に現地調査を依頼し、見積もりを取得します。費用だけでなく、実績、対応、廃棄物の処理方法なども比較検討します。
- アスベスト(石綿)調査の実施:
- 一定規模以上の解体工事や改修工事を行う場合、事前にアスベスト含有の有無を調査することが法令で義務付けられています 。調査の結果、アスベストが使用されている場合は、法令に基づいた適切な除去作業が必要となり、追加費用が発生します。
- アスベスト調査費用は、原則として建物の所有者が負担します 。
- 各種届出:
- 建設リサイクル法に基づく届出: 解体する建物の床面積が80平方メートルを超える場合、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。通常は解体業者が代行します。
- 道路使用許可申請(必要な場合): 解体工事に伴い、前面道路に作業車両を駐車したり、足場を設置したりする場合に必要です。
- 近隣への挨拶:
- 工事開始前に、解体業者とともに近隣住民へ工事の概要(期間、作業時間、騒音・振動対策など)を説明し、理解と協力を求めることがトラブル防止のために重要です。
- ライフラインの停止・撤去手配:
- 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの供給を停止し、必要に応じてメーターや配管・配線の撤去を依頼します。
- 解体工事の実施:
- 足場や養生シートの設置、内装材の撤去、建物本体の解体、基礎の撤去、整地といった流れで工事が進められます。
- 廃棄物の適正処理:
- 解体工事で発生した木くず、コンクリートがら、金属くずなどの産業廃棄物は、法令に基づいて適正に分別・処理されなければなりません。不法投棄は厳しく罰せられます。
- 建物滅失登記の申請:
- 建物を取り壊した後、1ヶ月以内に法務局に対して「建物滅失登記」を申請する義務があります 。これを怠ると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、登記簿上建物が存在し続けることになり、固定資産税が誤って課税され続けるリスクもあります 。
- 建物滅失登記は、自分で行うことも可能ですが(必要書類の取得費用として数千円程度 )、手続きが煩雑なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。その場合の費用相場は5万円前後です 。
解体にかかる費用(構造別・広さ別目安)
解体費用は、建物の構造、延床面積、立地条件、付帯物の有無、アスベスト含有の有無など、様々な要因によって大きく変動します。
費用の主な内訳:
- 建物本体の解体工事費: 建物を壊す作業そのものにかかる費用。
- 付帯工事費: 建物以外のもの(ブロック塀、門、カーポート、庭石、庭木、浄化槽、井戸など)の撤去費用。
- 廃棄物運搬処分費: 解体で発生した廃材を処理場まで運搬し、処分するための費用。廃材の種類や量によって変動します。
- 諸経費: 仮設工事費(足場、養生シートなど)、重機回送費、アスベスト調査・除去費用(該当する場合)、官公庁への申請書類作成費用、現場管理費など。
構造別・坪単価の目安: 一般的に、頑丈な構造ほど解体手間と費用がかかります。
- 木造: 3万円~5万円/坪
- 鉄骨造(S造):
- 軽量鉄骨造:4万円~6万円/坪程度(では坪4~5万円、では鉄骨造全体で坪3.4万~4.7万円とやや幅あり)
- 重量鉄骨造:5万円~7万円/坪程度(では坪5~6万円)
- 鉄筋コンクリート造(RC造): 6万円~8万円/坪
延床面積30坪の家の場合の解体費用相場:
- 木造: 約90万円~150万円
- 鉄骨造: 約120万円~180万円(では102万円~141万円、では120万円~180万円)
- 鉄筋コンクリート造(RC造): 約180万円~240万円(では105万円~240万円、では180万円~240万円)
費用を左右するその他の主な要因:
- 立地条件: 前面道路の幅が狭く大型重機やトラックが進入できない場合、手作業が増えたり小型車両での搬出になったりして費用が割高になります。
- 残置物の量: 家の中に家具や家電、ゴミなどが多く残っている場合、その処分費用が別途かかります。事前に自分で処分しておくと費用を抑えられます。
- アスベスト含有の有無: アスベストが使用されている場合、専門業者による除去作業が必要となり、高額な追加費用が発生します。
- 地中埋設物: 解体後に地中からコンクリートガラや以前の建物の基礎などが見つかった場合、その撤去費用が追加で発生することがあります。
6: 家屋解体費用の目安(延床面積30坪の場合)
| 建物の構造 | 坪単価目安 | 30坪の場合の総費用目安 | 費用を左右する主な要因 | 情報源 |
| 木造 | 3万~5万円/坪 | 90万~150万円 | 残置物、アスベスト、庭木・塀の有無、前面道路幅 | |
| 鉄骨造 | 4万~7万円/坪 (軽量/重量で変動) | 120万~180万円 (目安) | 同上、鉄骨の種類(軽量か重量か) | |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 6万~8万円/坪 | 180万~240万円 (目安) | 同上、コンクリートの厚み、配筋状況 |
この表はあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって費用は大きく異なります。正確な費用を知るためには、必ず複数の専門業者に見積もりを依頼しましょう。
解体に関する補助金制度
多くの地方自治体では、倒壊の危険性がある老朽家屋や、管理不全な空き家の解体に対して、費用の一部を補助する制度を設けています。これらの制度を活用することで、解体費用の負担を軽減できる可能性があります。
例えば、東京都墨田区では「老朽危険家屋除却費等助成金」という制度があります 。
- 不良住宅を対象とした除却費の助成:
- 内容: 住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合、除却費用を助成。
- 助成金額: 除却工事費の1/2で、上限50万円。ただし、建築基準法上の接道義務を満たさない「無接道敷地」に存する不良住宅の場合は上限100万円。
- 主な条件: 事前診断で不良住宅と判定されること、申請者が区税等を滞納していないこと、補助金の交付決定後に工事契約・着工することなど。
- 土地無償貸与を前提とした除却費の助成:
- 内容: 管理不全で危険な状態の建築物の除却後の跡地を、区へ原則10年間無償で貸与することを条件に、除却費用を助成。区は跡地をポケットパークなど公共目的で利用。
- 助成金額: 除却工事に要した費用で、上限200万円。
- 主な条件: 上記不良住宅の条件に加え、土地所有者であること、除却後の土地無償貸与契約を区と締結することなど。
このような補助金制度は、各自治体によって名称、対象となる建物の条件、補助金額、申請手続きなどが異なります。ご自身の空き家が所在する市区町村の役場(建築指導課、住宅課、空き家対策担当課など)に問い合わせるか、「自治体名 + 空き家 解体 補助金」といったキーワードでインターネット検索して調べてみましょう。国土交通省のウェブサイトなどでも、全国の支援制度に関する情報がまとめられている場合があります 。
選択肢④:空き家を「リフォーム・リノベーション」する

空き家をそのまま放置するのではなく、手を加えて再生させる「リフォーム」や「リノベーション」も有力な選択肢です。自己利用、賃貸、売却といった目的に応じて、適切な改修を行うことで、空き家の価値を高め、新たな可能性を引き出すことができます。
リフォームのメリット・デメリット(自己利用、賃貸、売却目的)
メリット:
- 住環境の向上(自己利用目的): 自分のライフスタイルや好みに合わせて間取りを変更したり、最新の設備を導入したりすることで、快適な住空間を実現できます。
- 賃料アップ・入居率向上(賃貸目的): 水回り設備の更新や内装の一新、現代的なニーズに合わせた間取り変更などを行うことで、より高い賃料設定や早期の入居者確保が期待できます。
- 売却価格の上昇・早期売却(売却目的): 購入希望者の目に魅力的に映るようなリフォームを施すことで、売却価格のアップや、より早い時期での売却につながる可能性があります。ただし、過度なリフォームは費用対効果が見合わない場合もあるため注意が必要です。
- 資産価値の向上: 建物の機能性やデザイン性を高めることで、不動産としての資産価値を向上させることができます。
- 補助金・税制優遇の活用: 耐震、省エネ、バリアフリーなどの特定のリフォームに対しては、国や自治体から補助金が出たり、税金の優遇措置を受けられたりする場合があります。
デメリット:
- 高額な費用: 工事の規模や内容によっては、数百万円から数千万円単位の費用がかかることがあります。
- 工事期間の発生: リフォーム内容によりますが、数週間から数ヶ月の工事期間が必要となり、その間は物件を使用できません。
- 期待した効果が得られないリスク: 多額の費用をかけてリフォームしても、必ずしも賃料が大幅に上がったり、希望価格で売却できたりするとは限りません。市場のニーズや物件の特性を考慮した計画が重要です。
- 建物の構造的な制約: 古い建物の場合、構造上の問題から希望通りの間取り変更が難しかったり、基礎や柱の補強に追加費用がかかったりすることがあります。
リフォーム費用の目安(工事規模別)
リフォーム費用は、工事の範囲や使用する素材・設備のグレードによって大きく変動します。以下は一般的な目安です。
部分リフォーム :
- トイレ交換・内装: 10万円~50万円
- キッチン交換(システムキッチン導入など): 50万円~200万円
- 浴室交換(ユニットバス化など): 50万円~150万円
- 内装(壁紙・床材の張り替えなど): 1平方メートルあたり5,000円~15,000円
- 外壁塗装・屋根塗装/修繕: 合わせて100万円~300万円程度(では外壁・屋根塗装で30~140万円とあるが、では屋根・外壁修繕で150~300万円と幅がある)
全体的なリフォーム・リノベーション :
- フルリノベーション(間取り変更、内装・設備一新など): 500万円~2,000万円前後。
- 築年数が古い物件や、基礎・柱の補強工事が必要な場合、大幅な間取り変更を伴う場合は、さらに高額になることがあります 。
- 古民家再生リフォーム: 伝統的な工法や素材を活かしつつ現代的な快適性を加えるため、2,000万円以上かかることも珍しくありません 。
特定の目的を持ったリフォーム :
- バリアフリーリフォーム(手すり設置、段差解消、通路拡幅など): 50万円~200万円
- 断熱性能向上リフォーム(窓・壁の断熱材交換、内窓設置など): 100万円~300万円
- 耐震補強工事: 基礎や柱の補強など、規模により200万円~500万円程度かかることもあります。
7: 主なリフォーム箇所と費用目安
| リフォーム箇所/内容 | 費用相場 | ポイント・注意点 | 情報源 |
| キッチン | 50万~200万円 | システムキッチンのグレード、壁付けか対面か等で変動。 | |
| 浴室 | 50万~150万円 | ユニットバスのグレード、在来工法からの変更などで変動。 | |
| トイレ | 10万~50万円 | 便器の種類(節水型、タンクレストイレ等)、内装工事の有無で変動。 | |
| 内装(壁紙・床) | 1㎡あたり5千~1.5万円 | 素材の種類(クロス、フローリング、畳等)で変動。 | |
| 外壁塗装 | 80万~150万円程度 (30坪の場合) | 塗料の種類(シリコン、フッ素等)、足場の有無で変動。 | (屋根と合わせて30-140万) |
| 屋根修繕/塗装 | 50万~200万円程度 | 塗装、葺き替え、カバー工法等、屋根材の種類で変動。 | (外壁と合わせて30-140万) |
| 耐震補強 | 100万~500万円以上 | 現状の耐震性能、補強範囲(壁、基礎等)により大きく変動。 | (基礎・柱補強200-500万) |
| 断熱改修 | 100万~300万円 | 窓交換、内窓設置、壁・床・天井への断熱材施工等。 | |
| バリアフリー化 | 50万~200万円 | 手すり設置、段差解消、スロープ設置、浴室・トイレ改修等。 | |
| フルリノベーション | 500万~2,000万円以上 | 間取り変更の規模、内装・設備のグレード、構造補強の有無で変動。 |
この表は、一般的なリフォーム費用の目安です。実際の費用は、物件の状態や選択する素材、依頼する業者によって大きく異なりますので、必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
活用できる補助金・助成金・税制優遇(国・自治体:耐震、省エネ、バリアフリーなど)
空き家のリフォーム・リノベーションには、国や地方自治体が提供する様々な支援制度を活用できる場合があります。これらの制度をうまく利用することで、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。主な支援内容は、補助金(助成金)の給付と税制優遇(所得税控除、固定資産税減額)です。
国の主な制度:
- 耐震リフォーム関連 :
- 所得税の控除: 現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%(限度額を超える部分は5%)が所得税から控除されます。最大控除額は62.5万円。対象は昭和56年5月31日以前に建築された自己居住用家屋で、令和7年12月31日までの工事完了が要件です。
- 固定資産税の減額: 工事完了翌年度分の固定資産税が1/2減額されます(家屋面積120平方メートル相当分まで)。
- 省エネリフォーム関連 :
- 所得税の控除: 断熱改修(窓、壁、床など)や高効率給湯器の設置など、一定の省エネ改修工事を行った場合に、工事費用に応じた額が所得税から控除されます。令和7年12月31日までの工事完了が要件です。住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン減税(年末ローン残高の0.7%を最大10年間控除、リフォームの場合の借入限度額2,000万円 )も検討できます。
- 固定資産税の減額: 一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額される措置があります(令和8年3月31日までの工事完了が対象)。
- 住宅省エネ2025キャンペーン : 国土交通省、経済産業省、環境省が連携して行う大規模な補助金事業群です。
- 先進的窓リノベ2025事業: 高断熱窓への改修に対し、工事内容に応じて定額補助(上限200万円/戸)。
- 給湯省エネ2025事業: 高効率給湯器(エコキュート、エネファーム、ハイブリッド給湯器など)の設置に対し、機種に応じて定額補助(例:エコキュート6~13万円/台)。
- 賃貸集合給湯省エネ2025事業: 既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ等への取替を支援。
- これらの補助金を利用するには、工事を行う施工業者がキャンペーンの登録事業者である必要があります。また、同一工事箇所について複数の制度に重複して申請することはできません。
- バリアフリーリフォーム関連 :
- 所得税の控除: 手すりの取り付け、段差解消、通路拡幅などのバリアフリー改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限200万円)の10%(限度額を超える部分は5%)が所得税から控除されます。最大控除額は60万円。対象者には年齢(50歳以上など)や要介護認定などの要件があります。令和7年12月31日までの工事完了が要件です。
- 固定資産税の減額: 工事完了翌年度分の固定資産税が1/3減額されます(家屋面積100平方メートル相当分まで)。新築後10年以上経過した住宅であることなどの条件があります。
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業 :
- 住宅の性能向上(耐震性、省エネ性、劣化対策など)や子育て世帯向け改修などを行う場合に、費用の1/3を補助。補助上限額は、認定を取得しない場合で80万円/戸、長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合は160万円/戸(三世代同居対応改修などを実施する場合は上限額が引き上げられる場合あり)。
- 子育てエコホーム支援事業 :
- 子育て世帯・若者夫婦世帯が行う一定の省エネ改修や子育て対応改修などに対し補助。リフォームの場合、工事内容に応じて上限30万円/戸(既存住宅を購入してリフォームを行う場合は上限60万円/戸など、条件により変動)。
- 介護保険における住宅改修費支給 :
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差解消などのバリアフリー改修を行う場合、実際の改修費用の7~9割(所得に応じて変動)が支給されます。支給上限基準額は20万円(つまり、最大18万円の支給)。
地方自治体の制度: 国だけでなく、都道府県や市区町村も独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。これらは国の制度と併用できる場合もあるため、積極的に情報を収集しましょう。
- 東京都の例 :
- 「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」として、高断熱窓や太陽光発電設備の設置などを支援する複数の事業があります(例:既存住宅における省エネ改修促進事業)。
- 市区町村の例:
- 東京都北区「空き家活用改修助成事業」: 空き家をシェアハウスなど共同居住型として活用する場合の改修費用を助成(上限150万円、費用の2/3)。
- 東京都墨田区「民間賃貸住宅改修支援事業」:
- 高齢者世帯等向け改修:空き住戸のバリアフリー化や共用部分の改修費用を助成(住戸部分上限20万円~30万円、共用部分上限100万円など、費用の2/3)。
- 住宅確保要配慮者向け改修:専用住宅として改修し東京都に登録する場合の費用を助成(住戸部分上限50万円、子育て仕様加算あり。共用部分上限100万円など、費用の2/3)。
- これらの自治体の制度を利用する際は、多くの場合、工事契約前に申請が必要となる点に注意が必要です 。
リフォームに関する補助金や税制優遇は種類が多く、適用条件も細かいため、全てを個人で把握するのは困難です。また、国の制度は予算上限に達すると早期に締め切られることもあります 。リフォームを検討する際は、まずどのような工事を行いたいかを明確にし、それに対応する支援制度がないか、リフォーム業者や自治体の窓口、専門家のウェブサイトなどで情報収集することが重要です。複数の制度が適用できる場合もあるため、最大限に活用するための計画的なアプローチが求められます。
8: 主なリフォーム減税・補助金制度(国)の概要
| 制度名 | 対象工事例 | 主な支援内容(控除/補助) | 主な適用要件(対象者、住宅、期間等) | 情報源 |
| 耐震リフォーム減税 | 現行耐震基準適合工事 | 所得税:工事費の10%(上限250万)等、最大62.5万控除 固定資産税:翌年度1/2減額 | 昭56.5.31以前建築の自己居住家屋。R7.12.31まで(所得税) | |
| 省エネリフォーム減税 | 断熱改修、高効率給湯器設置等 | 所得税:工事費に応じた控除(ローン型/投資型あり) 固定資産税:翌年度減額 | 自己居住家屋。R7.12.31まで(所得税) | |
| バリアフリーリフォーム減税 | 手すり設置、段差解消等 | 所得税:工事費の10%(上限200万)等、最大60万控除 固定資産税:翌年度1/3減額 | 50歳以上、要介護者等。自己居住家屋。R7.12.31まで(所得税) | |
| 子育てエコホーム支援事業 | 省エネ改修、子育て対応改修等 | 補助金:上限30万円/戸~(条件により変動) | 子育て・若者夫婦世帯等。 | |
| 先進的窓リノベ2025事業 | 高断熱窓への改修 | 補助金:上限200万円/戸(定額) | 登録事業者による施工。 | |
| 給湯省エネ2025事業 | 高効率給湯器設置 | 補助金:機種に応じ定額(例:エコキュート6~13万円/台) | 登録事業者による施工。 | |
| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 性能向上リフォーム等 | 補助金:上限80万~160万円/戸(費用の1/3、条件により変動) | ||
| 介護保険住宅改修 | 手すり設置、段差解消等 | 費用支給:上限20万円の範囲で7~9割 | 要介護・要支援認定者。 |
この表は国の主要な支援制度をまとめたものです。各制度には詳細な要件や申請期限があるため、必ず最新情報を確認し、専門家にも相談しながら活用を検討してください。
リフォームプロセスと主な手順
空き家のリフォーム・リノベーションは、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 目的の明確化と情報収集:
- 何のためにリフォームするのか(自己利用、賃貸、売却)、予算はどのくらいか、どのような空間にしたいか、といった目的や要望を明確にします。
- インターネットや雑誌、ショールームなどで情報を集め、イメージを具体化します。
- リフォーム会社の選定と相談:
- 複数のリフォーム会社に相談し、実績や得意分野、提案力、担当者との相性などを比較します。空き家のリフォーム実績が豊富な会社を選ぶと安心です。
- 現地調査とプランニング:
- リフォーム会社に現地調査を依頼し、建物の状態や構造、法的制約などを確認してもらいます。
- 要望を伝え、具体的なリフォームプランと概算見積もりを作成してもらいます。
- 詳細見積もりと契約:
- プランが固まったら、詳細な見積もり(工事内容、使用する素材・設備、工期、支払い条件など)を提示してもらいます。内容を十分に確認し、納得できれば工事請負契約を締結します。
- 工事着工:
- 近隣への挨拶を済ませ、工事を開始します。工事中は、定期的に現場を確認し、進捗状況や仕上がりをチェックすると良いでしょう。
- 工事完了と検査・引き渡し:
- 工事が完了したら、リフォーム会社とともに仕上がりを検査します。問題がなければ、引き渡しを受け、残金を支払います。
- 補助金・減税の申請手続き:
- 利用する補助金や税制優遇制度の申請手続きを行います。多くは工事完了後の申請となりますが、制度によっては工事着工前の申請や認定が必要な場合もあるため、事前に確認し、必要な書類を準備しておくことが重要です。
知っておきたい法律とサポート体制
空き家問題に対処する上で、関連する法律や利用できるサポート体制を理解しておくことは非常に重要です。これらは、所有者の責任を明確にするとともに、適切な対応を後押しするものです。
「空家等対策特別措置法」の概要と近年の改正点
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)は、空き家問題の深刻化に対応するため、2015年5月に施行されました。この法律は、国民生活の安全・安心の確保、生活環境の保全、そして空き家の活用促進を目的としています 。
主な内容としては、市町村による空き家の実態調査、所有者等に対する空き家の適切な管理に関する情報提供や助言・指導、そして放置すれば危険な状態等にある「特定空家」に対する措置(助言・指導、勧告、命令、行政代執行)などが定められています。
この空家法は、社会状況の変化や対策の進捗を踏まえ、2023年12月に改正法が施行され、内容が強化・拡充されました。主な改正点は以下の通りです 。
- 「管理不全空家」の新設:
- 従来の「特定空家」に至る前の段階として、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を「管理不全空家」と位置づけました。これにより、市町村はより早期の段階で所有者に対して指導・勧告を行うことが可能となり、固定資産税の住宅用地特例の解除といった措置も適用できるようになりました。
- 「空家等活用促進区域」の創設:
- 市町村が、空き家の活用を重点的に図るべきエリアを「空家等活用促進区域」として定めることができるようになりました。この区域内では、空き家の用途変更を伴うリフォームなどを行う際に、建築基準法の接道義務や用途規制を合理化(緩和)する特例措置を講じることが可能となり、空き家の多様な活用を後押しします。
- 緊急代執行制度の創設:
- 倒壊の危険が切迫しているなど、緊急性が高い特定空家については、従来の助言・指導、勧告、命令といった手続きを経ずに、市町村が迅速に行政代執行(解体など)を行えるようになりました。これにより、台風などの自然災害時における迅速な安全確保が期待されます。
- 所有者の責務強化:
- 空き家の所有者等に対し、従来の適切な管理の努力義務に加え、国や地方公共団体が実施する空き家に関する施策に協力するよう努めることが求められるようになりました。
- 財産管理人制度の円滑化:
- 相続放棄などにより所有者が不存在となった空き家や、所有者不明の空き家について、市町村長が家庭裁判所に対して財産管理人の選任を請求できるようになりました。これにより、所有者不在の空き家の管理や処分が進めやすくなります。
2023年の法改正は、一方で管理が不十分な空き家に対する行政の介入を強化し、所有者の責任をより重くするとともに、もう一方では空き家の活用を促進するための新たな仕組みを導入するという、二つの側面を持っています。これは、空き家問題の負の側面を抑制しつつ、空き家を地域の資源として再生させようという国の総合的な戦略の表れと言えます。所有者にとっては、単に罰則が強化されたと捉えるだけでなく、これらの新しい枠組みが自身の空き家問題解決の新たな選択肢や支援に繋がる可能性も理解しておくことが重要です。
自治体の相談窓口や支援制度の探し方
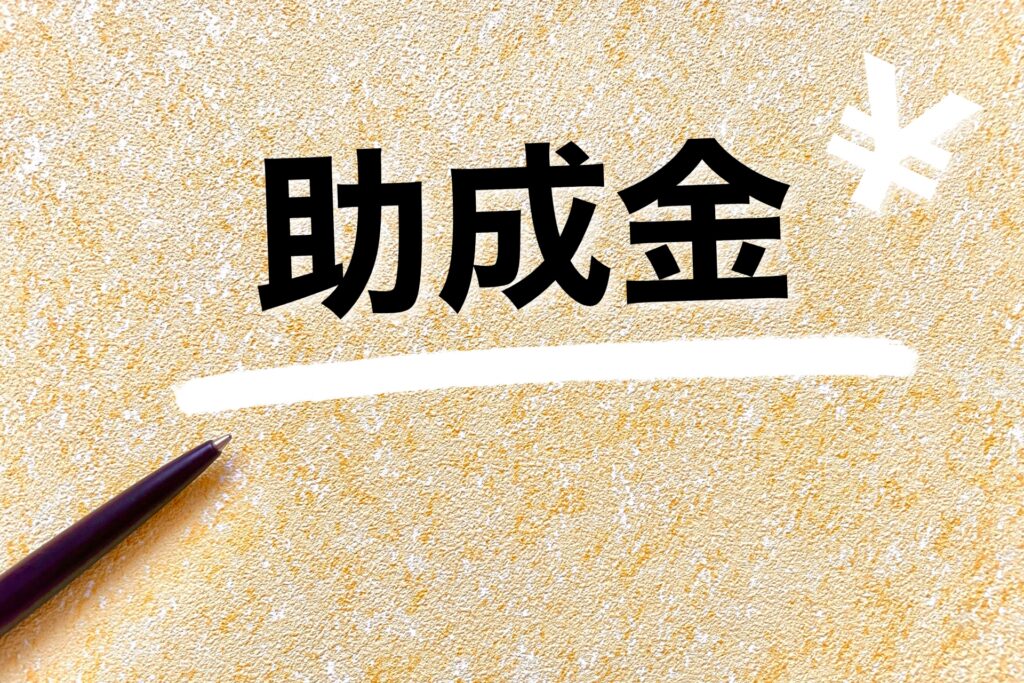
空き家に関する悩みや問題を抱えたとき、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することが解決への第一歩です。
- 市区町村の相談窓口:
- 多くの市区町村では、空き家に関する専門の相談窓口(例:建築指導課、住宅課、都市計画課、空き家対策担当課など)を設置しています。これらの窓口では、空き家の管理方法、活用方法、解体やリフォームに関する助成制度、法的な手続きなどについて相談することができます。
- 多くの市区町村で空き家対策の人員等が不足しているとの指摘もあり、対応の充実度には地域差がある可能性も考慮に入れる必要があります。
- 空家等管理活用支援法人:
- 改正空家法に基づき、市町村は空き家の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人、民間企業などを「空家等管理活用支援法人」として指定することができます 。これらの法人は、空き家所有者からの相談対応、空き家の活用を希望する者とのマッチング支援、空き家の管理代行など、より専門的できめ細やかなサポートを提供することが期待されています。
- 国の機関や関連団体のウェブサイト:
- 国土交通省のウェブサイトでは、空き家対策に関する最新情報や、各自治体の支援制度の検索ページなどが提供されています 。
- 住宅金融支援機構のウェブサイトでも、「空き家関連情報サイト」が開設されており、空き家の取得やリフォームに関する融資制度や補助金情報などを探すことができます 。
- インターネット検索:
- 「お住まいの自治体名 + 空き家相談」や「自治体名 + 空き家 補助金」、「自治体名 + 空き家バンク」といったキーワードで検索することで、関連情報を見つけることができます。
これらの相談窓口や情報を活用し、専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の空き家に最も適した対策を進めていくことが重要です。
おわりに:あなたの空き家に最適な選択を
ここまで、空き家を所有する方が直面する可能性のある様々な状況と、それに対する具体的な選択肢(売却、賃貸、解体、リフォーム)について、費用、補助金、税金、手続きの観点から詳しく解説してきました。どの選択肢が最適かは、空き家の状態、立地条件、そして何よりも所有者ご自身の意向や経済状況によって大きく異なります。
賢い選択のためのキーポイント再確認
最後に、後悔のない賢い選択をするために、改めて押さえておきたいキーポイントをまとめます。
- 現状把握の徹底: まずはご自身の空き家の状態(権利関係、建物の老朽度、法規制など)を正確に把握することが全ての始まりです。必要に応じて専門家による調査も検討しましょう。
- 多角的な比較検討: 各選択肢(売却、賃貸、解体、リフォーム)には、それぞれメリットとデメリット、そして費用、税金、手続きが伴います。一つの側面に囚われず、総合的に比較検討することが重要です。
- 情報収集と制度の活用: 国や自治体が提供する補助金や税制優遇制度は多岐にわたります。これらを積極的に情報収集し、活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
- 専門家への相談: 不動産会社、税理士、建築士、土地家屋調査士、弁護士など、それぞれの分野の専門家は、皆様が抱える問題に対して的確なアドバイスを提供してくれます。一人で悩まず、積極的に相談しましょう。
- 将来を見据えた判断: 目先の対応だけでなく、数年後、数十年後を見据えた長期的な視点で、どの選択がご自身やご家族にとって最も良い結果をもたらすかを考えることが大切です。
積極的な管理への第一歩
空き家問題は、残念ながら放置していても自然に解決することはありません。むしろ、時間の経過とともにリスクが高まり、選択肢が狭まってしまう可能性すらあります。しかし、見方を変えれば、空き家は適切な対応を施すことで、新たな価値を生み出す「資産」にもなり得ます。
本ガイドが、空き家という課題に直面している皆様にとって、現状を整理し、具体的な行動を起こすための一助となれば、これに勝る喜びはありません。まずは小さな一歩でも構いません。専門機関に相談してみる、情報を集めてみるなど、積極的な管理への第一歩を踏み出されることを心より願っております。
墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください!適切な売却プランをご提案いたします。


