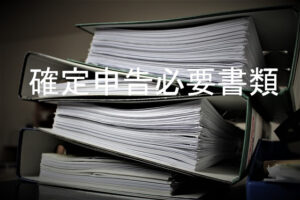減価償却費とは?収益物件における節税のカギ
減価償却費は、収益物件の運営において重要な経費の一つであり、適切に計上することで節税につなげることができます。不動産投資を行う際には、この仕組みを理解し、長期的な視点で計画を立てることが成功のポイントです。以下では、減価償却費の概要と計算方法、注意点について詳しく解説します。
減価償却費とは?
減価償却費とは、建物や設備といった資産の購入費用を耐用年数にわたって分割して経費計上するものです。物理的な劣化や老朽化によって資産価値が徐々に減少していくことを、税法上のルールに基づいて計算し、経費として認める仕組みです。
ポイント: 購入費用を一括で経費にすることはできません。ただし、税法上のルールにより「1点の取得価格が10万円未満の資産」や「少額減価償却資産特例を適用する場合(30万円未満の資産)」については、購入した年度に全額を経費として計上することが認められる場合もあります。
減価償却の対象となる資産
1.建物
- 物件そのもの(建物部分)が対象です。
- 例: アパート、マンション、戸建て住宅。
2.設備
- 建物内の設備や備品も対象になります。
- 例: エアコン、給湯器、照明設備、キッチン設備。
3.外構
- 建物周辺の付属物も含まれます。
- 例: フェンス、駐車場、外階段。
土地は対象外
土地は時間が経過しても価値が減少しないため、減価償却の対象にはなりません。物件購入時には、建物部分と土地部分の価格を明確に分けて記載する必要があります。
耐用年数と計算方法
減価償却費は、税法で定められた「法定耐用年数」に基づいて計算されます。耐用年数は資産の種類や構造、用途によって異なります。
耐用年数の例(建物の場合)
- 木造: 22年
- 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm以下): 19年
- 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm超~4mm以下): 27年
- 重量鉄骨造(骨格材の厚さ4mm超): 34年
- 鉄筋コンクリート造(RC造): 47年
中古物件の場合の耐用年数(簡易計算式)
中古物件では、法定耐用年数を過ぎた場合、以下の計算式で耐用年数を求めます。
耐用年数=(法定耐用年数×0.2)+経過年数 ※ 少数点以下は切り上げ。
減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法には、主に以下の2つがあります。
1.定額法
毎年同じ金額を経費として計上する方法です。
減価償却費=購入価格×90%÷耐用年数
※ 90%は残存価額(取得価額の10%)を控除するため。
2.定率法
初年度に多くの減価償却費を計上できる方法です。近年では、建物部分については定額法が原則となっています。
減価償却費を計上するメリット
1.節税効果が大きい
減価償却費は実際に現金の支出を伴わない「非現金経費」です。そのため、物件運用によるキャッシュフローを維持しつつ、所得税や住民税を軽減することが可能です。
2.中古物件でさらに有利に
中古物件は耐用年数が短く設定されるため、減価償却費を早期に多く計上できる可能性があります。これは特に節税を重視する投資家にとって有利なポイントです。
3.長期的な資産管理に役立つ
減価償却を適切に計上することで、資産の価値や収支状況を正確に把握することができます。
減価償却費計上時の注意点
1.土地と建物の価格配分
不動産取得時に土地と建物の価格を明確に区分する必要があります。契約書や固定資産税評価額を基に正確に計算しましょう。
2.減価償却資産台帳の作成
税務申告時には、減価償却資産台帳を作成し、資産ごとの減価償却費を計上する必要があります。
3.税理士への相談
減価償却の計算は複雑な場合があるため、プロのアドバイスを受けることが推奨されます。
まとめ
減価償却費は、収益物件を所有する上で最も重要な経費の一つです。法定耐用年数や計算方法を理解し、適切に申告することで、キャッシュフローを維持しながら税負担を軽減できます。中古物件を含めた不動産投資を検討する際には、減価償却費を含む長期的な収支計画を立てることが成功への鍵となるでしょう。
墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください!適切な売却プランをご提案いたします。