不動産売却 役所で建築計画概要書が発行されない場合
第1章:建築計画概要書が存在しない理由の解明
不動産売却において概要書が取得できないという問題に直面した際、まず行うべきは、その「なぜ」を正確に理解することである。原因を特定することで、その後の対応策の方向性が定まり、買主や金融機関への説明も論理的かつ説得力のあるものになる。
1.1. 概要書の法的根拠と目的
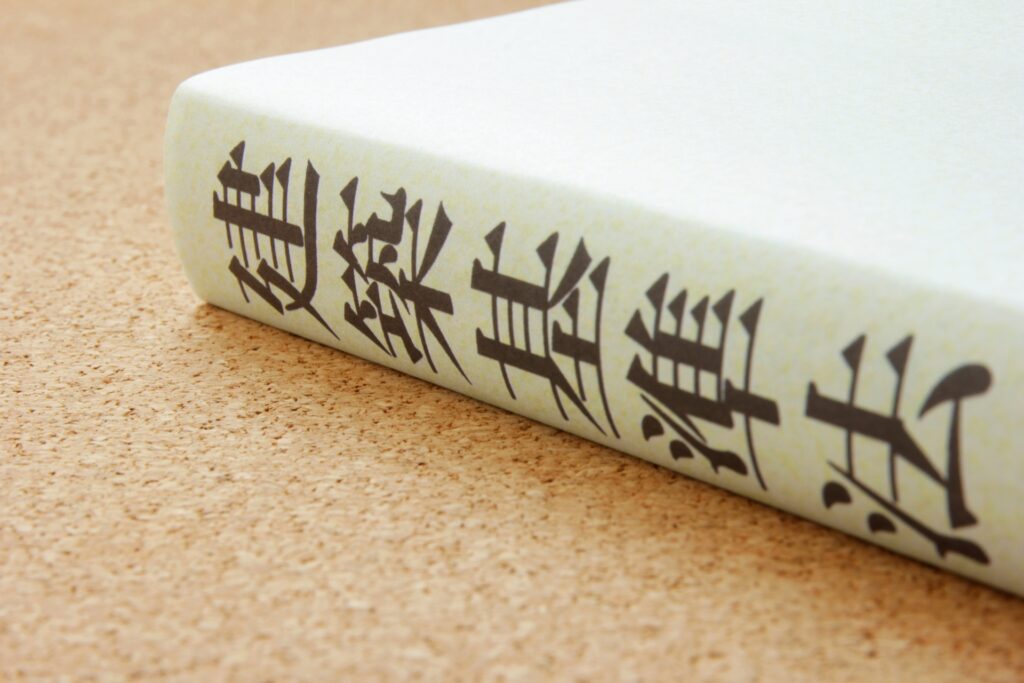
概要書は、建築基準法第93条の2に基づき定められた制度である 。その創設目的は、建築計画の概要を一般の閲覧に供することにより、周辺住民の協力のもとで違反建築物の建築を未然に防止し、さらには無確認建築物や違反建築物の売買を防ぐことにある 。これにより、善意の買主を保護する役割も担っている。
この書類は、建築確認申請時に提出される書類の一つであり、その内容は不動産の遵法性を確認する上で極めて重要である。一般的に、概要書は以下の3面で構成される。
- 第一面: 建築主、設計者、工事施工者など、建築に関わった関係者の氏名や住所、資格などが記載される。これにより、建物の責任の所在が明確になる 。
- 第二面: 物件の核心的なデータが列挙される。敷地の地名地番、敷地面積、建築面積、延べ面積、建物の構造、高さ、階数といった物理的な情報に加え、用途地域、建ぺい率、容積率といった建築基準法上の規制に関する数値が記載されている 。これらの数値は、建物の法的な規模が適正であるかを確認するための根拠となる。
- 第三面: 付近見取図と配置図が記載される。特に配置図は、敷地境界線、敷地内における建物の位置、隣地境界線や道路からの距離(セットバック)、接道状況など、視覚的に遵法性を確認するための不可欠な情報源である 。
不動産取引において、宅地建物取引業者が作成する重要事項説明書には、これらの建築基準法上の制限に関する事項を記載する義務があり、概要書はその調査の最も基本的な資料として活用される 。
1.2. 概要書が存在しない4つの主要な理由
概要書が発行されない理由は、主に以下の4つに大別される。
- 理由1:制度施行前の建築(「1971年以前」の壁) 概要書の閲覧制度が施行されたのは、1971年(昭和46年)1月1日である 。したがって、この日より前に建築確認を受けた建物については、制度自体が存在しなかったため、原理的に概要書は存在しない。これは最も分かりやすい歴史的な理由である。
- 理由2:行政の「記録保存の空白期間」(1971年~1999年頃) これが最も一般的であり、かつ誤解されやすい理由である。1971年に制度が開始されたものの、特定行政庁(市や県など)に対して、概要書を「当該建築物が滅失し、又は除却されるまで」保存することを義務付けたのは、1999年(平成11年)5月1日に施行された建築基準法施行規則の改正からである 。 この改正以前、多くの自治体は独自の保存年限規定に基づき、一定期間が経過した古い記録を法的に廃棄していた。そのため、1970年代や1980年代に建築された建物の場合、概要書が存在しないのは紛失や違法建築の隠蔽が理由ではなく、自治体の公式な記録管理方針に基づく正当な廃棄処分によるものである可能性が高い 。 実際に、各自治体のウェブサイトを見ると、概要書の保管開始年度には大きなばらつきがある。例えば、東京都世田谷区では概ね1979年度(昭和54年度)以降 、港区では1989年(平成元年)4月1日以降 、新宿区では1995年(平成7年)4月1日以降 となっており、全国一律ではないことがわかる。この「行政の空白期間」の存在を理解することが、問題解決の第一歩となる。
- 理由3:法的な適用除外 すべての建築物や工作物に概要書が存在するわけではない。以下のようなケースは、制度上、作成・保存の対象外となる。
- 国や地方公共団体などが建築主となる「計画通知」による建築物の一部(特に2007年6月以前のもの) 。
- 擁壁や煙突といった「工作物」、およびエレベーターなどの「昇降機」や「建築設備」 。
- 理由4:偶発的な紛失または未整理 頻度は低いものの、災害による焼失や物理的な紛失、あるいは古い記録が整理されずに書庫のどこかに埋もれてしまい、発見が困難になっているケースも考えられる 。
この問題の核心は、特に理由2の「記録保存の空白期間」に起因する場合、その建物の遵法性に問題があるのではなく、当時の行政システムに起因する記録の不存在であるという点にある。この点を正確に把握し、買主や関係者に説明することが極めて重要である。不動産取引の専門家は、単に「概要書がない」と伝えるのではなく、「当該物件の建築年代(例:1980年代)においては、市の記録保存規定により、現在では概要書が保管されていないため発行されません」と、その背景にある制度的な理由を明確に伝えるべきである。これにより、物件固有の欠陥であるとの誤解を避け、問題を「解決可能な行政手続き上のハードル」として再定義することができる。
表1:建築計画概要書不存在の要因診断チャート
| 想定される原因 | 対象となる年代・建築物 | 特徴 | 最初の確認ステップ |
| 制度施行前の建築 | 1971年1月1日以前に建築確認 | 制度自体が存在しない | 登記簿で建築年月日を確認 |
| 記録保存の空白期間 | 1971年~1999年頃に建築確認 | 自治体が記録を合法的に廃棄 | 役所の建築指導課に当時の記録保存方針を問い合わせる |
| 法的な適用除外 | 公共建築物の一部、工作物、昇降機など | 法的に作成・保存義務がない | 建築物の種類(用途)を確認する |
| 偶発的な紛失・未整理 | 全ての年代で可能性あり | 例外的な事象 | 役所に対し、地番・建築主名・建築年など複数の検索条件で再調査を依頼する |
第2章:ドミノ効果:概要書なしで売却する際の重大なリスク

概要書が存在しないという事実は、単なる書類の欠落にとどまらない。それは不動産取引の根幹を揺るがし、法務、金融、価格形成の各側面で連鎖的なリスク(ドミノ効果)を引き起こす。
2.1. 証明責任の転換:主要な証拠なくして遵法性をいかに証明するか
通常、建物の遵法性は、計画段階の適法性を示す「建築確認済証」および「概要書」と、計画通りに施工されたことを示す「検査済証」によって証明される 。概要書がなければ、その中でも特に重要な配置図が失われる。これにより、建ぺい率や容積率、斜線制限、そして隣地や道路との離隔距離といった、建築基準法の根幹をなす規制への適合性を客観的に示すことが極めて困難になる 。
この瞬間、遵法性の「証明責任」は、公的書類から売主へと完全に転換される。売主は、自らの費用と労力で、その建物が単なる「違反建築物」ではなく、少なくとも建築当時は適法であった「既存不適格建築物」であること、あるいは現行法にも適合していることを証明しなければならなくなる 。前者は是正命令や除却命令のリスクを伴い、事実上、市場での売買が不可能である一方、後者は一定の制約のもとで売買が可能である。この区別を明確にできない限り、取引は前に進まない。
2.2. 重要事項説明のジレンマ:宅地建物取引業者の法的責任
宅地建物取引業法第35条に基づき、不動産会社(宅地建物取引業者)は、売買契約が成立するまでの間に、買主に対して重要事項説明書を交付し、物件に関する重要な事項を説明する法的義務を負う 。この説明事項には、建築基準法に基づく建築制限などが含まれており、その調査には通常、概要書が用いられる 。
概要書がない状況で、単に「概要書は不存在」と記載するだけでは、宅地建物取引業者の善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を果たしたとは到底言えない。なぜ存在しないのか、そして概要書に代わる遵法性の確認をどのように行ったのかを具体的に説明しなければ、説明義務違反とみなされるリスクがある。万が一、売却後に建物の重大な法的不備が発覚した場合、買主から契約不適合責任を追及され、売主および仲介した不動産会社は損害賠償請求などの深刻な法的紛争に巻き込まれる可能性がある 。
2.3. 融資の壁:金融機関が「ノー」と言う理由
金融機関にとって、不動産は融資の「担保」である。その担保価値の根幹は、物件の流動性と法的安定性にある。遵法性が不明確な物件、すなわち是正命令や最悪の場合には除却命令のリスクを内包する「違反建築物」の可能性がある物件に対して、金融機関が融資を実行することはない 。概要書がないという事実は、金融機関の審査担当者にとって、まさにこの最大のリスクを想起させる赤信号となる。
特に、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】のような公的性格の強い住宅ローンは、技術基準が極めて厳格である。適合証明書の交付が融資の前提条件であり、そのためには検査済証の存在など、建物の適法性が明確に証明される必要がある 。概要書がなく、代替手段による遵法性の証明がなされていない物件は、この適合証明を取得できず、融資の対象から外れることはほぼ確実である。
2.4. 経済的損失:価値下落の連鎖
融資が受けられないという事実は、買主の範囲を、自己資金で一括購入できる一部の富裕層や、特殊な物件を専門に扱う不動産投資家などに著しく限定してしまう 。
市場経済の原理に基づき、需要が急減すれば価格は暴落する。遵法性が不明確な物件や、結果として「再建築不可」と判断されるような物件の市場価格は、近隣の同等な適法物件と比較して30%から50%、場合によってはそれ以上の大幅なディスカウントを余儀なくされる 。売却活動は長期化し、買主からは足元を見られた価格交渉が頻発することになる 。
この一連の流れは、まさに負のスパイラルである。概要書の不存在が「遵法性の不確実性」を生み、それが「金融機関の融資拒否」につながり、結果として「買主層の限定」と「市場価値の暴落」を引き起こす。この因果関係を深く理解することが、売主に対して、次章で詳述する専門的な調査への投資がいかに重要であるかを説得するための鍵となる。建築士による調査費用は単なる出費ではなく、この負のスパイラルを断ち切り、物件を再び融資可能な一般市場へと引き戻し、その本来の価値を回復させるための不可欠な投資なのである。
第3章:法的地位を再構築するためのステップ・バイ・ステップガイド

概要書の不存在という壁に直面したとき、不動産取引の専門家は「調査担当者」としての役割を担う必要がある。場当たり的な対応ではなく、体系的な調査を通じて、失われた遵法性の証明を再構築するプロセスが求められる。このプロセスは、大きく3つのフェーズに分けられる。
3.1. フェーズ1:基礎書類の収集(デスク調査)
物理的な現地調査に先立ち、役所の窓口や手元の資料から、遵法性の輪郭を浮かび上がらせるための基礎的な書類を収集する。
- ステップ1:台帳記載事項証明書を取得する
- 概要: これは、特定行政庁が保管する建築確認台帳に記載されている事項を証明する公的な書類である 。
- その効力: この証明書の最大の価値は、建築確認済証の交付年月日・番号に加え、完了検査済証の交付年月日・番号を証明できる点にある 。検査済証が交付されたという記録は、建物が竣工当時に建築基準法に適合していると検査機関によって判断されたことを示す極めて強力な証拠となる 。
- 限界: 一方で、この書類には概要書のような配置図は含まれていないため、建物の配置に関する遵法性を直接証明することはできない 。また、建物が非常に古い場合や、自治体によっては台帳自体が散逸している、あるいは営利目的の請求と見なされて発行が拒否されるケースも存在する 。
- ステップ2:固定資産評価証明書から手がかりを得る
- 概要: 固定資産税の課税根拠となる評価額を証明する書類である 。
- 有用な情報: この書類には、公的に登録された家屋の床面積、構造、建築年月日などが記載されている 。
- 活用方法: ここに記載された床面積と、不動産登記簿謄本に記載された床面積を比較する。もし両者に差異があれば、それは未登記の増築が行われた可能性を示唆する重要な警告サインとなる。この書類自体が遵法性を証明するものではないが、建物の物理的な履歴に関する一貫性のある情報を構築する上で役立つ。
- ステップ3:「最良の代替資料」– オリジナルの設計図書を探す
- 概要: 新築時の詳細な平面図、立面図、そして最も重要な配置図を含む、建築図面一式のことである 。
- 重要性: 建築確認申請時に使用された、押印のあるオリジナルの設計図書一式が残っていれば、それは失われた概要書を補って余りある最良の代替資料となる。なぜなら、概要書に記載されているすべての情報、およびそれ以上の詳細な情報が含まれているからである 。これらの図書は、元の所有者、施工した建設会社、あるいは設計した建築士事務所が保管している可能性がある。
3.2. フェーズ2:専門家による現地調査と遵法性検証
デスク調査で得られた情報を基に、専門家による物理的な検証へと進む。ここでは、目的の異なる2つの調査が存在することを明確に理解する必要がある。
- 選択肢A:建物状況調査(インスペクション)
- 調査範囲: これは、既存住宅状況調査技術者(インスペクター)が、建物の物理的な状態を評価するための調査である。構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分を中心に、ひび割れ、雨漏りの痕跡、シロアリ被害の有無などを非破壊で目視調査する 。
- 費用と時間: 一般的に5万円~10万円程度で、所要時間は2~4時間ほどである 。
- 決定的な限界: この調査は、建物の「劣化状況」を評価するものであり、「法的な遵法性」を判断するものではない 。買主に対して建物のコンディションに関する安心感を与える上では価値があるが、概要書の不存在という核心的な問題を解決するものではない。
- 選択肢B:最終解決策 – 建築士による遵法性調査
- 調査範囲: これは、一級建築士などの専門家が、現存する建物が「建築された時点の」建築基準法や関連法令に適合していたかどうかを検証する、本格的な法務調査である 。
- プロセス: 建築士は、フェーズ1で収集した全ての書類を精査し、現地で詳細な測量を実施する。必要であれば、現況から図面を復元(復元図面作成)し、当時の建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制など、あらゆる法的要件との整合性を分析する 。
- 成果物: 調査結果は、専門的な見解として「法適合状況調査報告書」にまとめられる 。この専門家による報告書こそが、失われた概要書に代わる、遵法性を証明する権威ある文書となる。
- 費用と時間: これは大規模な作業であり、費用は建物の規模や複雑さによって30万円から100万円以上になることも珍しくなく、期間も1ヶ月から3ヶ月程度を要する 。
3.3. フェーズ3:法的に堅牢な重要事項説明書の作成
調査の最終目的は、その結果を正確に重要事項説明書に反映させ、透明性が高く、法的に防御可能なディスクロージャー(情報開示)を完成させることである。
- 不適切な記載例: 「建築計画概要書は発行されませんでした。」 この一文だけでは、調査義務を放棄したと見なされかねず、極めて不十分である。
- 適切かつ防御可能な記載例: 「本物件について、管轄の〇〇市役所に照会したところ、建築当時(〇〇年頃)の記録は市の保管規定に基づき現存しないため、建築計画概要書は発行できないとの回答でした 。」 「つきましては、売主の責任と負担において、本物件の遵法性に関する以下の調査を実施し、その結果を本書に添付します。」 「1. 台帳記載事項証明書(写し添付): 本書面により、〇〇年〇月〇日付で完了検査済証(番号:第〇〇号)が交付されていることが確認できます。これは、本建物が竣工当時に完了検査に合格したことを示すものです 。」 「2. 法適合状況調査報告書(写し添付): 〇〇建築士事務所(一級建築士 〇〇 〇〇)が〇〇年〇月〇日付で作成した本報告書は、現地調査および分析の結果、現存する建物が建築当時の建築基準法に適合していると結論付けています 。」 「買主は、建築計画概要書に代わるものとして、上記各報告書を受領し、その内容を理解した上で本契約を締結するものです。」
この一連のプロセスは、単一の書類(概要書)に依存する標準的な取引とは異なり、複数の証拠を積み重ねていく階層的な証明活動である。税務書類、登記情報、台帳記載事項証明書、そして最終的には建築士の専門的見解という「証拠のポートフォリオ」を構築する。このアプローチにより、重要事項説明書は、将来の法的責任を誘発しかねない「地雷」から、売主と仲介業者を守る強力な「法的防御の盾」へと昇華する。それは、「問題がある」というネガティブな報告ではなく、「既知の行政上の課題が特定され、専門的な手法によって解決された」というポジティブな報告へと、取引の性質そのものを転換させるのである。
表2:代替調査手法の比較マトリックス
| 調査手法・書類 | 提供される情報 | 推定費用 | 推定期間 | 法的効力・主な用途 |
| 固定資産評価証明書 | 課税評価額、登録上の床面積、構造、建築年 | 1,000円未満 | 即日~数日 | 補足データ。登記情報との照合による矛盾点の洗い出し。 |
| 台帳記載事項証明書 | 建築確認・検査済証の交付履歴(番号・日付) | 1,000円未満 | 即日~数日 | 過去の適法性の強力な証拠。ただし図面はない。 |
| 建物状況調査 | 建物の物理的な劣化状況(ひび割れ、雨漏り等) | 5万円~10万円 | 1~2週間 | 買主への物理的な安心材料の提供。遵法性の証明にはならない。 |
| 建築士による遵法性調査 | 建築当時の法規への適合性(建ぺい率、容積率等) | 30万円~ | 1~3ヶ月 | 最終的な遵法性の証明。融資審査や重要事項説明の根拠となる決定的な書類。 |
第4章:自治体ごとの差異への対応:極めて重要な最初の電話
これまで見てきたように、概要書の記録保存に関する方針は、自治体によって驚くほど異なる 。したがって、いかなる調査を開始する前にも、まず管轄の自治体の担当部署、通常は建築指導課やそれに類する部署へ直接問い合わせることが、絶対不可欠な第一歩となる。
4.1. 二つとして同じ市はない
全国一律のルールが存在しない以上、インターネット上の一般的な情報だけに頼るのは危険である。対象物件の所在地を管轄する特定行政庁の方針を直接確認することが、時間と費用の浪費を避けるための最短ルートである。
4.2. 自治体への主要な質問リスト
担当者との電話または窓口での相談の際には、以下の点を明確に質問する必要がある。
- 「貴庁における、〇〇年代(例:1970年代、1980年代)に建築確認された建物の、建築計画概要書の公式な保存期間について教えてください。」
- 「その年代の記録は、公式な規定に基づいて廃棄処分されたという認識でよろしいでしょうか?」
- 「もし概要書が不存在の場合、当該物件の台帳記載事項証明書を発行していただくことは可能ですか?」
- 「その台帳には、完了検査済証が交付されたという記録は残っていますか?」
4.3. 記録(ペーパートレイル)の重要性
もし自治体の担当者が、記録が公式に廃棄されたことを口頭で確認した場合は、その方針が記載された公的な通知やウェブページの写しなど、何らかの書面で示してもらえないか依頼することが望ましい。たとえ担当部署からのEメールの返信であっても、そのやり取り自体が、売主側が誠実に調査を行った証拠となり、重要事項説明の際の添付資料として価値を持つことがある。
結論:詳細な調査によって成約可能な取引へと転換する

建築計画概要書の不存在は、不動産取引において法務、金融、そして実務の各側面に深刻なリスクをもたらす重大な障害である。この問題に直面したとき、安易な楽観論や場当たり的な対応は、将来の法的紛争や大幅な経済的損失に直結する。
しかし、本稿で詳述したように、この課題に対する解決の道筋は明確に存在する。その核心は、単一の書類を求めるのではなく、積極的かつ多層的な調査プロセスを遂行することにある。それは、基礎的な公的書類の収集から始まり、専門家による物理的・法的な検証へと進み、最終的には、その全プロセスを誠実かつ網羅的に開示する、法的に堅牢な重要事項説明をもって完結する。
確かに、一級建築士による完全な遵法性調査は、決して安価ではない。しかし、その投資コストは、遵法性が不明確なまま放置した場合に被るであろう、30%から50%にも及ぶ壊滅的な資産価値の毀損と比較衡量されなければならない。ほとんどのケースにおいて、この調査は、物件の市場性を回復させ、その本来の価値を引き出すために不可欠な、費用対効果の極めて高い投資であると言える。
最終的に、この種の事案は、経験の浅い担当者や売主自身が独力で対応できる領域を超えている。この複雑な状況を成功裏に乗り切るためには、建築関連法規に精通し、非標準的な案件の取り扱いに実績のある、高度な専門性を持つ不動産取引のプロフェッショナルの関与が不可欠である。徹底した調査と透明性の高い情報開示という戦略を貫くことで、乗り越えがたいと思われた壁は、最終的に、関係者全員が納得する取引へと姿を変えるのである。
墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください!適切な売却プランをご提案いたします。


