不動産売却で損しないための自分でできる土地測量 完全ガイド

不動産、特に土地を売却する際、多くの売主が「少しでも費用を抑えたい」「自分でできることは自分でやりたい」と考えるのは自然なことです。その思いがしばしば「土地の面積くらい、自分で測れるのではないか?」という疑問につながります。しかし、この一見単純な作業には、不動産取引の根幹を揺るがしかねない大きな落とし穴が潜んでいます。
不動産取引におけるトラブルの主要な原因の一つが、登記簿に記載されている「公簿面積」と、実際に測量した「実測面積」の不一致です 。この差異は、特に古い時代に登記された土地では決して珍しくなく、時に数百万単位の金銭トラブルや契約解除にまで発展します。
不動産売却を検討する売主が、専門家さながらの視点で土地の測量に取り組むための実践的なガイドを提供することです。ただし、これは専門家による測量の代替を推奨するものではありません。むしろ、ご自身で予備的な測量を行うことで、所有する不動産が抱える「リスクの大きさ」を把握するための強力なリスク評価ツールとして活用いただくことを目指します。本稿では、まず自分でできる測量の具体的な手順を解説し、次にその限界と、安全な取引を保証するための専門的な解決策について深く掘り下げていきます。
第1章 なぜ正確な測量が成功する売却の礎となるのか

数平方メートルの面積の違いが、なぜ円滑な取引と高額な訴訟の分かれ目になるのでしょうか。この章では、土地の面積が持つ金銭的・法的な重要性を解き明かし、正確な測量がなぜ不可欠なのかを明らかにします。
1.1. 土地売買の二つの世界:公簿売買と実測売買
土地の売買契約には、大きく分けて二つの方法が存在します。それぞれの特性とリスクを理解することが、すべての始まりです。
- 公簿売買(こうぼばいばい): 登記所に記録されている登記記録上の面積(公簿面積)を基準に売買代金を決定し、取引を行う方法です 。この契約では、将来的に実測面積との差異が判明しても、原則として売主・買主双方が代金の増減を請求しない、という特約が付されるのが一般的です 。
- 実測売買(じっそくばいばい): 実際に土地を測量した面積(実測面積)を基準に売買代金を決定する方法です。契約時には公簿面積で暫定的に契約し、引き渡しまでに実測を行い、最終的に平方メートル単価(m2単価)などに基づいて代金を精算します 。近年の一般的な住宅地の取引では、面積の曖昧さをなくしトラブルを避けるため、この実測売買が主流となっています 。
公簿売買は、測量費用がかからず、契約までのスピードが速いという利点があります。そのため、広大で測量が困難な山林の取引や、ごく最近測量が行われ、誤差の可能性が極めて低い土地などで選択されることがあります 。しかし、一般的な住宅地、特に登記情報が古い土地で安易に公簿売買を選択すると、売主・買主双方に重大なリスクをもたらします 。
1.2. 金銭的な利害:あなたが負うわけにはいかない数字のゲーム
面積の差異がもたらす金銭的な影響は、決して軽視できません。具体的な数字で見てみましょう。
例えば、1㎡あたりの単価が30万円の土地があったとします。公簿面積が100㎡、しかし実測面積が90㎡だった場合、その価値には明確な差が生まれます 。
- 公簿売買の場合: 30万円 × 100㎡ = 3,000万円
- 実測売買の場合: 30万円 × 90㎡ = 2,700万円
このケースでは、300万円もの差額が発生します。売主の視点では、もし実測面積が公簿より広ければ売却益が増える可能性がありますが 、逆に狭いことを知らずに公簿売買で売却してしまうと、後述する法的責任を問われるリスクがあります。買主の視点では、実測面積が公簿より狭い場合、「存在しない土地」に対して過大な代金を支払うことになります 。特に、測量技術が未熟だった時代の登記では、誤差が20%に達するケースも報告されており、そのリスクは計り知れません 。
1.3. 土地の契約不適合責任
契約不適合責任とは、売買契約において引き渡された目的物(土地)が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。土地の面積が契約内容と著しく異なる場合、これは「数量」に関する契約不適合と見なされる可能性があります 。
たとえ公簿売買の特約を結んでいたとしても、当事者の想定をはるかに超えるような著しい面積の差異が発覚した場合、「特約で許容される範囲を超えている」として、買主から代金減額請求や契約解除を求められる紛争に発展する可能性があります 。このような事態を避けるための最も確実な防御策は、専門家による正確な測量を行い、その結果に基づいて契約内容を明確にすることです 。
この背景を理解すると、公簿売買と実測売買の選択が単なる手続き上の違いではなく、リスクの戦略的な配分であることが見えてきます。古い測量図しかない、あるいは測量図自体が存在しない土地で売主が公簿売買を強く推すことは、面積差異のリスクを買主に転嫁しようとしていると解釈されかねません。賢明な買主やその代理人である不動産会社は、このリスクを敏感に察知し、リスクを相殺するための大幅な価格交渉を要求するか、あるいはその物件の購入自体を見送るでしょう 。
現代の不動産市場では、金融機関が融資の際に境界が明確でない土地を敬遠する傾向もあり 、取引の「確実性」そのものが価値を持つようになっています。この市場の変化により、専門家による測量は、もはや単なる「選択肢」ではなく、適正な市場価格で不動産を売却するための「前提条件」となりつつあるのです。
表1:公簿売買と実測売買の比較
| 特徴 | 公簿売買(売主) | 公簿売買(買主) | 実測売買(売主) | 実測売買(買主) |
| 価格の基準 | 登記簿上の面積 | 登記簿上の面積 | 実際の測量面積 | 実際の測量面積 |
| 費用 | 測量費用不要(安い) | 測量費用不要(安い) | 測量費用負担(高い) | 原則費用負担なし |
| スピード | 速い | 速い | 時間がかかる | 時間がかかる |
| 面積差異リスク | 後で発覚した場合、責任を問われる可能性 | 面積が少ないリスク(損をする可能性) | リスクなし | リスクなし |
| 売却後の紛争リスク | 高い | 高い | 低い | 低い |
| 主な用途 | 山林、超広大な土地、最新の測量図がある場合 | 左記に同じ | 一般的な住宅地、市街地の土地取引 | 左記に同じ |
第2章 机上調査:公的資料を確認する
実際にメジャーを握る前に、まず行うべきは「机上調査」です。測量は、根拠となる公式な図面がなければ、単なる当て推量に過ぎません。この章では、売却準備の第一歩として、法務局で入手すべき重要書類とその解読方法を解説します。
2.1. 法務局で必須の図面を手に入れる
最初のステップは、あなたの土地を管轄する法務局で、以下の公的な図面を取得することです 。
- 重要書類1:地積測量図(ちせきそくりょうず) これは最も重要な書類で、土地の形状、各辺の長さ、境界点の座標値、そして境界標の種類などが詳細に記載されています 。いつ測量されたものかを示す「作成年月日」も記録されており、図面の信頼性を測る上で決定的な情報となります 。
- 重要書類2:公図(こうず) これは、あなたの土地が隣接地とどのように接しているか、その相対的な位置関係や形状を示した地図です 。ただし、その精度は様々で、明治時代に作成された大まかな見取り図のようなものから、現代の技術で作成された精度の高いものまで、品質には大きなばらつきがあります。
これらの書類は、以下の方法で誰でも取得できます。
- 法務局の窓口で取得: 1通450円の手数料(収入印紙で支払い)で、公式な証明書として取得できます 。
- オンラインで取得(登記情報提供サービス): 1通361円で、PDFデータとしてインターネット経由で取得できます 。こちらは公的な証明力はありませんが、個人で内容を確認する分には十分かつ安価です 。
請求には、住所(住居表示)ではなく、土地の「地番」が必要です。地番が不明な場合は、権利証(登記識別情報)を確認するか、法務局に備え付けのブルーマップで調べる、あるいは窓口で相談することができます 。
2.2. 地積測量図を解読して隠されたヒントを読む
入手した地積測量図を、ただ眺めるだけでは不十分です。その信頼性を正しく評価する方法を学びましょう。
- 作成年月日がすべてを物語る: 図面の信頼性を判断する最も重要な手がかりは、作成年月日です。一般的に、測量技術が未熟だった昭和50年代以前に作成された図面は、精度が低い可能性があります 。一方で、世界測地系に基づく座標値の記録が義務化された2005年(平成17年)以降に作成されたものは、非常に高い信頼性を持ちます 。
- 見つけるべき重要情報:
- 境界線と辺長: 土地の各辺の長さ。これが現地での実測値と比較する際の基準となります。
- 境界標の種類(標種): 図面には、境界点に「コンクリート杭」や「金属標」といった、どのような種類の境界標が設置されているかが記載されていることがあります 。これは、次の現地調査で何を探すべきかという重要なヒントになります。
- 座標値: 近年作成された図面には、各境界点の座標値が記載されています。これは精度のゴールドスタンダードであり、万が一境界標がなくなってしまっても、この座標値から正確に境界点を復元することが可能です 。
この机上調査の段階で、そもそも「地積測量図が存在しない」という事実が判明すること自体が、極めて重要な情報となります。これは、あなたの土地の境界が過去に一度も専門家によって明確にされておらず、その面積の根拠が信頼性の低い公図や過去の慣習にしかない、という強烈な危険信号です。この場合、安易な公簿売買は極めてハイリスクであり、自分で測量する意味も薄れます。売却可能な資産とするためには、専門家による「確定測量」が推奨されるのではなく、絶対的に必要である、という結論がこの時点で導き出されるのです 。
このプロセスは、売主の意識を「私はこの土地を所有している」という事実認識から、「私が所有している土地に関する法的な記録データは、このような品質である」という客観的な資産評価へとシフトさせます。この意識変革こそが、不動産取引を成功に導くための本質的な第一歩と言えるでしょう。
第3章 現地調査 予備的な自己測量の実践ガイド

机上調査で得た図面を手に、いよいよ現地での測量です。この章では、あくまで予備的な確認として、ご自身で土地の寸法を測るための具体的な手順を解説します。ここでの目的は、第2章で入手した書類の内容を「地上で検証する」ことです。
3.1. 土地の四隅にある境界標を見つけ出す
最初におこなうことは、地積測量図に示された境界点に対応する、「境界標」を現地で見つけ出すことです 。
- 探すべき場所: 土地の角、ブロック塀やフェンスの基礎部分、擁壁の上や下などを重点的に探します。多くの場合、長年の間に土や落ち葉、雑草などで埋もれてしまっているため、小さなスコップなどで慎重に掘り返す必要があります 。
- 境界標の種類: 一般的な境界標には以下のようなものがあります。それぞれの特徴を知ることで、発見が容易になります。
- コンクリート杭: 最も一般的な境界標。頭頂部に十字(+)や矢印(↑)の印があり、十字の中心や矢印の先端が境界点を示します 。
- 金属標・金属鋲: コンクリートやアスファルトに埋め込まれた金属製のプレートや鋲。特に公道との境界など、官民境界でよく見られます 。
- 石杭: 古くから使われている御影石などでできた杭。耐久性が高く、中心に丸い窪みや十字が刻まれていることが多いです 。
- プラスチック杭: 近年使われるようになった杭で、頭部がプラスチック製で金属プレートが付いているものもあります 。
表2:主な境界標の種類と見方
| 境界標の種類(画像例) | 主な材質 | 一般的な印 | 境界点の示し方 | 備考 |
| コンクリート杭 | コンクリート | 十字(+)、矢印(↑) | 十字の中心、矢印の先端が境界点を示す。 | 最も一般的なタイプ。 |
| 金属プレート・鋲 | 金属(真鍮、アルミ等) | 十字(+)、矢印(↑) | 十字の中心、矢印の先端が境界点を示す。 | 公道との境界でよく見られる。「境界」「〇〇市」等の刻印があることも。 |
| 石杭 | 御影石など | 丸い窪み、十字(+) | 窪みや十字の中心が境界点を示す。 | 古い土地で使われていることが多い。耐久性が高い。 |
| プラスチック杭 | プラスチック、金属 | 矢印(↑) | 矢印の先端が境界点を示す。 | 比較的新しいタイプ。 |
| 壁面取り付けプレート | 金属 | 矢印(↑) | 矢印が指し示す壁の角などが境界点となる。 | 杭が設置できない場所で使われる。 |
3.2. 測定の道具とテクニック
境界標を発見したら、次はその間の距離を測定します。
- 道具: 短い距離や障害物が多い場所では、JIS規格1級などの精度が高いスチール製コンベックス(メジャー)が適しています。見通しの良い長い直線距離では、レーザー距離計が非常に便利です。
- レーザー距離計の正しい使い方:
- 電源を入れ、測定の基準点(本体の底面か先端か)を設定します 。
- 本体の基準点を始点となる境界標にしっかりと当て、測定したい終点の境界標にレーザーを照射します 。
- 測定ボタンを押すと、瞬時に距離が表示されます。
- 注意点: レーザー距離計は、手ブレで誤差が生じやすいため、長い距離を測る際は三脚に固定すると精度が上がります 。また、強い日差しや雨天、測定対象が黒っぽい色やガラスのような透過・反射する素材の場合、正確に測定できないことがあります 。
3.3. 測定値から面積の概算計算方法
測定した辺の長さから、土地のおおよその面積を計算します。これはあくまで概算であることを忘れないでください。
- 単純な四角形の場合: 「縦 × 横」で計算できます。
- 不整形地の場合(三角形分割法): 土地を複数の重ならない三角形に分割します。そして、各三角形の3辺の長さ(a, b, c)を測定します。各三角形の面積は、ヘロンの公式を用いて計算し、最後にそれらを合計します。
- まず、s=(a+b+c)/2 を計算します。
- 三角形の面積は s(s−a)(s−b)(s−c)
で求められます。
このDIY測量の最終目的は、「決定的な答え」を出すことではありません。むしろ、「①現地で測定した辺の長さと、地積測量図に記載された辺の長さ」「②自分で計算した概算面積と、登記簿上の公簿面積」を比較することにあります。この比較によって、もし大きな食い違いがあれば、それは専門家による調査が必要な「危険信号」と判断できるのです。
この現地調査のプロセスは、売主に図面だけではわからない「現場の真実」を教えてくれます。例えば、境界標があるべき場所に隣家の塀が建っている「越境」の発見、工事によって境界標が動かされた形跡、あるいは境界標そのものの亡失など、売却前に解決すべき法的な問題をあぶり出すことがあります 。DIY測量は、単なる面積チェックから、不動産の健全性を診断する総合的なヘルスチェックへとその意味を変えるのです。
第4章 DIY測量の限界と専門家を呼ぶべき時

ここまでの手順で、あなたは所有する土地について、多くの売主よりも深い理解を得たはずです。しかし、ここからが最も重要な分岐点です。なぜDIY測量の結果に依存してはならないのか、その限界と、専門家の介入が不可欠となる深刻な事態について解説します。
4.1. なぜあなたの測量は「参考値」でしかないのか
まず、明確に理解すべきは、ご自身で行った測量の結果は、不動産取引において一切の法的効力を持たない「参考値」であるという事実です 。その理由は、技術的な正確性の欠如にあります。
- 専門機材の不在: 土地家屋調査士が使用するトータルステーションなどの測量機器は、ミリ単位の精度を保証しますが、市販のレーザー距離計やメジャーではその精度は望めません。
- 技術的な問題: 土地の傾斜やわずかな高低差を考慮した水平距離の計算、地球の丸みの補正などは専門的な知識と技術を要します 。
- 法的根拠の欠如: 専門家による測量は、不動産登記法などの法令に則った厳格な手順で行われます。DIY測量には、そのプロセスを保証するものが何もありません。
したがって、DIY測量の唯一の目的は、あくまで「公的な記録との間に、看過できないほどの大きなズレがないか」を確認するための、個人的なスクリーニングに過ぎません。
4.2. 紛争と越境の発覚
DIY測量の過程で最も深刻な発見は、「越境」です。越境とは、隣地の建物(屋根の軒先、壁など)や工作物(塀、フェンス)、あるいは樹木の枝や根などが、あなたの土地の境界線を越えて侵入している状態を指します 。
これは、売買対象の不動産における重大な瑕疵(欠陥)であり、売却を頓挫させる可能性があります。売主は、この問題を解決する義務を負います。解決策としては、越境物の撤去を求めるか、それが難しい場合は、将来の建て替え時には撤去することなどを定めた法的な「覚書」を隣地所有者と取り交わす必要があります 。
4.3. 隣人関係と境界立会いの壁
専門家による「確定測量」の核心部分は、境界立会いです。これは、土地家屋調査士、土地所有者、そして隣接するすべての土地の所有者(公道に面していれば行政の担当者も含む)が現地に集まり、境界点がお互いの認識で相違ないことを確認し、書面に署名・捺印する、極めて重要なプロセスです 。
しかし、ここで「立会いの拒否」という大きな壁にぶつかることがあります 。隣人との関係が悪化している、あるいは単に非協力的であるなどの理由で、立会いを拒否されるケースは少なくありません。
もし立会いを拒否された場合、問題解決の道は段階的に険しくなります。
- 専門家による交渉: まずは、中立的な第三者である土地家屋調査士が、隣人に対して立会いの重要性や、隣人自身にも「費用負担なく境界が確定する」というメリットがあることを説明し、交渉を試みます 。
- 筆界特定制度: 交渉が決裂した場合、法務局に申請することで「筆界特定登記官」という公的な立場の専門家が、資料調査や現地調査に基づき、職権で筆界(公法上の境界)の位置を特定する制度です。これは強力な判断材料となりますが、訴訟のような強制力はありません 。
- 境界確定訴訟: 最終手段です。裁判所に訴えを起こし、司法の判断によって境界線を法的に確定させます。これは非常に時間と費用がかかり、隣人との関係を決定的に破壊する可能性もある、最後の砦です 。
この法的な手続きの存在は、裏を返せば予防措置の価値を雄弁に物語っています。隣人関係が良好なうちに、売主が自発的に費用を負担して確定測量を行っておくことは、将来起こりうる訴訟費用や精神的苦痛、そして売却機会の損失といった計り知れないコストを回避するための、最も賢明で安価な投資なのです。境界が曖昧な土地の真のコストとは、測量費用そのものではなく、不確実性がもたらすあらゆるリスクの総和なのです。
第5章 専門家に依頼して確実性を得る
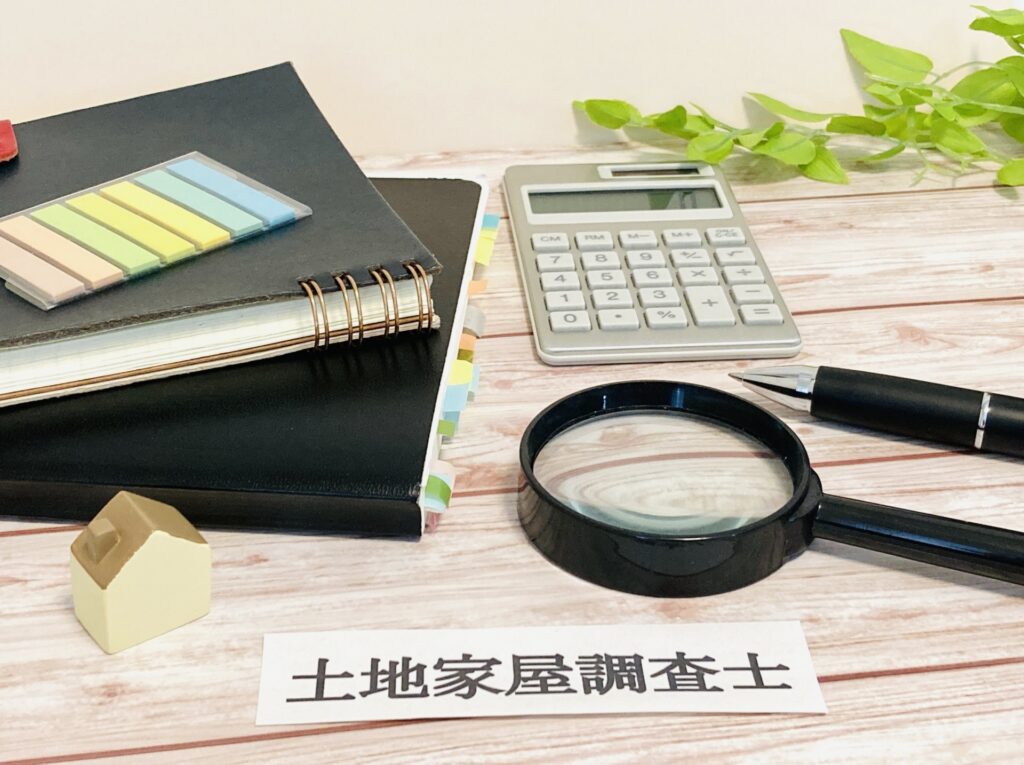
DIY測量でリスクの所在を把握した今、次の一手は専門家への依頼です。この章では、安全な取引を保証するためのプロフェッショナルな選択肢、その費用、そして信頼できる専門家の見つけ方を具体的に解説します。
5.1. 最適な専門家選び:土地家屋調査士と測量士の違い
まず、混同されがちな二つの国家資格の違いを明確に理解する必要があります。これは極めて重要です。
- 土地家屋調査士(とちかおくちょうさし): 法務省が管轄する法律の専門家です。不動産の「表示に関する登記」を目的とした測量を行うことが法的に許可された唯一の資格者であり、境界確定のプロセスを代理することもできます 。彼らはまさに「境界のプロフェッショナル」です。
- 測量士(そくりょうし): 国土交通省が管轄する技術の専門家です。道路やトンネルといった公共事業や、大規模な開発における測量を担いますが、登記を目的とした個人の土地の測量や境界確定業務は行えません 。彼らは「測量のプロフェッショナル」です。
結論として、不動産売却のために測量を依頼する場合、あなたが依頼すべき専門家は必ず土地家屋調査士となります 。
5.2. 二つの測量:「現況測量」と「確定測量」
土地家屋調査士に依頼する測量にも、目的と精度に応じて主に二つの種類があります。
- 現況測量(げんきょうそくりょう):
- 内容: 隣地所有者の立会いを行わず、現地のブロック塀やフェンスといった物理的な状況に基づいて、おおよその土地の形状や面積を測るものです 。
- 目的: 迅速かつ安価に現状を把握するための測量。建物の新築計画の初期段階などで利用されます 。
- 法的効力: 境界を法的に確定する力はありません 。
- 費用と期間: 費用は約10万円~20万円、期間は1週間程度が目安です 。
- 確定測量(かくていそくりょう):
- 内容: これが不動産取引におけるゴールドスタンダードです。法務局での資料調査、現地測量に加え、隣接するすべての土地所有者(官有地含む)との境界立会いを行い、全員の合意のもとで境界を確定させます 。
- 目的: 土地の境界と面積を法的に確定させること。安全な売買、土地の分筆、登記簿面積の修正(地積更正登記)には不可欠です 。
- 法的効力: 作成される「確定測量図」は、境界に関する極めて信頼性の高い公的な証明資料となります 。
- 費用と期間: 費用は高額で、隣地が民有地のみの場合は約35万円~50万円、公道など官有地との境界確定(官民査定)が必要な場合は約60万円~80万円以上になることもあります。期間も1.5ヶ月から3ヶ月以上を要します 。
表3:専門家による測量の費用内訳と概要
| 測量の種類 | 費用目安(民地のみ) | 費用目安(官民査定あり) | 主な作業内容 | 所要期間 | 主な用途 |
| 現況測量 | 10万円~20万円 | - | 現地状況の測量、現況図作成(境界立会いなし) | 約1週間 | 建築の初期計画、現状把握 |
| 確定測量 | 35万円~50万円 | 60万円~80万円以上 | 事前調査、現地測量、全隣地所有者との境界立会い、境界標設置、確定測量図・境界確認書作成 | 1.5ヶ月~3ヶ月以上 | 不動産売買、分筆登記、地積更正登記 |
確定測量の費用内訳(例)
- 事前調査(資料調査など): 6万円~10万円
- 測量業務(現地作業): 10万円~15万円
- 書類作成(図面、報告書): 3万円~5万円
- 境界確定業務(立会いなど): 2万円~10万円(隣地の数や官民査定の有無による)
- 登記費用(必要な場合): 1.5万円~3万円
5.3. 測量費用は誰が負担するのか?
測量費用を誰が負担するかについて、法律上の明確な定めはありません。しかし、不動産業界の慣行として、原則的に売主が負担します 。
その理由は、売主には境界が明確で瑕疵のない「クリーンな商品」を買主に引き渡す責任がある、という考え方に基づいています 。測量は、商品を市場に出すための準備の一環と見なされるのです。買主が強く購入を希望する場合などに、費用負担を交渉できる可能性はゼロではありませんが、それは例外的なケースです 。
5.4. 専門家の探し方:信頼できる土地家屋調査士を見つけるには
信頼できる専門家を探す最も確実な方法は、日本土地家屋調査士会連合会や、各都道府県にある土地家屋調査士会のウェブサイトに掲載されている名簿から探すことです 。不動産会社の紹介を受けることも一つの手ですが、複数の事務所から見積もりを取り、売却予定地のあるエリアでの業務経験などを確認した上で、納得して依頼することをお勧めします。
結論:賢明な売主が選ぶ、安全で高収益な売却への道
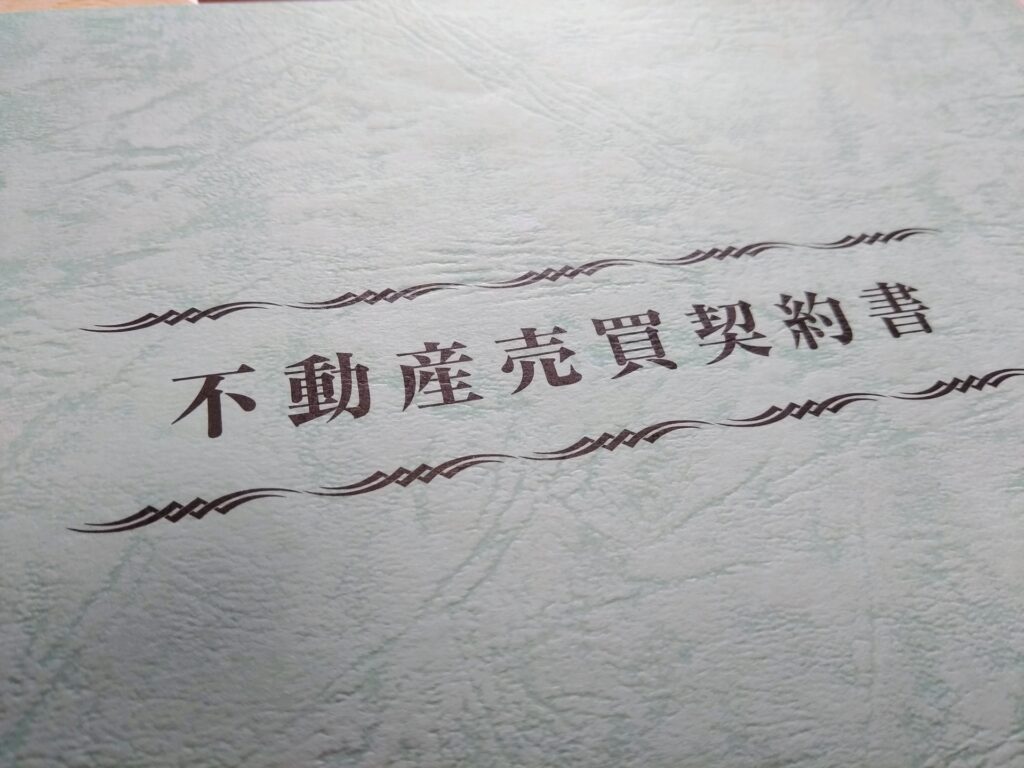
本稿を通じて、あなたは好奇心旺盛なDIY実践者から、情報に基づいた意思決定ができる賢明な売主へと歩みを進めました。ご自身での測量は、所有不動産のリスクを把握するための価値ある第一歩です。しかし、その結果だけを頼りに取引を進めることは、大きな危険を伴います。
最終的な結論は明確です。ほとんどの住宅地の売却において、DIY測量や古い情報に基づく公簿売買に頼ることは、「安物買いの銭失い」になる可能性が極めて高いと言えます。金銭的損失、法的な紛争、そして売却そのものの失敗という潜在的なリスクは、専門家への依頼費用をはるかに上回ります。
あなたの最も価値ある資産を守り、その価値を最大化し、円滑な取引を実現するための最も確実な道は、資格を持つ土地家屋調査士に確定測量を依頼することです。これは単なる出費ではありません。それは「確実性」への投資であり、あなたの不動産売却を成功に導くための、最も賢明な選択なのです。
墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください!適切な売却プランをご提案いたします。


