借地権建物の建物買取請求権:借地人の法的保護と地主の重要な責任

借地契約終了と建物買取請求権
借地契約の期間満了は、借地人にとっては強力な権利が発動する可能性を秘め、地主にとっては重大な義務を課される局面となります。それが「建物買取請求権」です。
この借地借家法の権利は、主に二つの目的を達成するために設計されています。
- 借地人の投下資本の回収:地主の土地に建物を建てるために投じた資本を、借地人が回収できるように保護するものです 。
- 社会経済的損失の防止:借地契約が終了したという理由だけで、まだ十分に利用価値のある建物を取り壊すという社会的な損失を回避します 。借地人は解体費用を負担する代わりに、建物の対価を得ることができます 。
ここで最も重要な点は、この権利が単なる交渉の申し入れやお願いではないということです。建物買取請求権は「形成権」と呼ばれる非常に強力な権利です。これは、借地人がこの権利を有効に行使した瞬間、借地人と地主との間で建物の売買契約が自動的に成立することを意味します。地主側にこれを拒否する法的な権利は一切ありません 。この一つの概念が、契約終了時における当事者間の力関係を根本的に決定づけるのです。
第1章 建物買取請求権の本質

1.1 法的根拠と立法の趣旨
建物買取請求権は、借地借家法第13条に明確に規定されています 。条文によれば、借地権の存続期間が満了し、契約が更新されない場合、借地権者は地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求できると定められています。
この制度の立法の趣旨は、旧借地法から受け継がれたものであり、歴史的に弱い立場に置かれがちであった借地人と地主との間の力関係を調整することにあります。法律は、借地人が所有する建物の利用と、そこから生じる利益を強力に保護しているのです 。
1.2 権利の不可侵性
借地契約書の中に、借地人の建物買取請求権を放棄させたり、排除したりする旨の特約があったとしても、その条項は法的に無効となります 。
これは「強行規定」と呼ばれるもので、地主が契約上の力関係を利用して、借地人からこの基本的な保護を奪うことを防ぐために設けられています。この原則の唯一の主要な例外は、第4章で詳述する特定の種類の定期借地権の場合のみです。
この法制度の構造は、地主の絶対的な財産権の自由よりも、投下資本の保全と借地人の生活保障を優先するという、明確な政策的判断を明らかにしています。地主が買取を拒否することも、契約によってこの権利を無効にすることもできないという事実は、立法府が借地人の建物を、保護されるべき重要な投資であり、国民経済に貢献するものと見なしていることを示唆しています。
この二重の保護構造を分析すると、立法府が、地主が借地人に対して権利放棄を強要するような力関係の不均衡が生じる可能性を予見していたことがうかがえます。その結果、地主は自身の土地に関する長期的な計画を立てる際、通常の借地契約の終了時には建物を買い取らなければならないという潜在的な金銭的負担を常に考慮に入れなければならなくなります。これは、地主の資産計画や土地開発戦略、そして土地そのもの(いわゆる「底地」)の金融的評価に深い影響を与えます。これにより、当事者間の関係は純粋に取引的なものではなく、長期的かつ共生的な視点を持つことが促されるのです。
第2章 権利行使の4つの柱(行使要件)

本章では、建物買取請求権を行使するために満たさなければならない4つの累積的な要件を詳細に解説します。一つでも欠ければ、権利の主張は無効となります。
2.1 要件1:借地権の存続期間の満了
この権利は、契約期間が公式に終了した後にのみ行使可能です。契約期間中に、借地人が単に転居したいという理由で地主に建物の買取を求めることはできません 。転勤や家族の介護といったやむを得ない個人的な事情による中途解約であっても、この権利は発生しません 。
2.2 要件2:契約の更新がないこと
これは重要かつ多義的な要件です。「契約の更新がない」という状況は、いくつかの形で発生します 。
- ケースA:地主による正当事由のある更新拒絶 借地人が更新を請求したものの、地主がこれを拒絶し、かつその拒絶に法律上認められる「正当事由」がある場合です 。「正当事由」は、地主自身がその土地を使用する必要性が高い場合などが該当しますが、その認定のハードルは高く、地主が借地人に対して立退料を支払うことで補完されるケースも少なくありません 。
- ケースB:借地人による更新請求の不実施 借地人自身が契約更新を請求せず、代わりに直ちに建物買取請求権を行使する場合です 。
- ケースC:黙示の更新に対する地主の異議 借地人が期間満了後も土地の使用を継続し、それによって更新の意思を黙示的に示した場合に、地主が「正当事由」をもってこれに異議を述べた場合です 。
2.3 要件3:建物の存在
借地契約の期間満了時に、借地人が所有する建物が土地上に物理的に存在している必要があります 。
この「建物」には、主たる構造物だけでなく、庭木、石垣、門扉など、借地人が権原に基づいて土地に付属させた物も含まれます 。ただし、建物内の家具や什器といった動産は対象外です 。
建物が非常に古い場合でも、構造物としての体裁を保っていれば要件を満たします。その価値は低いかもしれませんが、重要なのはその「存在」です 。
2.4 要件4:借地人による買取請求の意思表示
借地人は、地主に対して権利を行使する意思を明確に表示しなければなりません 。
この意思表示は口頭でも有効とされていますが、後日、権利行使の有無や時期をめぐる紛争を避けるためにも、配達証明付きの内容証明郵便のような、記録が残る形式で行うことが強く推奨されます 。
「契約更新請求権」と「建物買取請求権」の関係性を深く考察すると、借地人にとって戦略的な分岐点が見えてきます。借地人は単一の道筋を強制されるわけではありません。
まず、その土地に住み続けたい借地人の基本的な選択肢は、契約更新を請求することです。もしこの請求が「正当事由」をもって拒絶された場合、建物買取請求権が金銭的なセーフティネットとして機能します 。しかし、法は借地人に対し、更新請求をせずに、直ちに買取請求を行う選択肢も認めています 。
これは、借地人が「その土地での生活を継続すること」と「建物を資産として清算し、移転すること」のどちらを望むかという戦略的な選択を可能にしていることを意味します。もし後者を望むのであれば、更新の交渉を試みることなく、強制的に売買契約を成立させることができるのです。
このことは、地主側にとって重要な示唆を与えます。地主は、借地人が当然更新を望むだろうと安易に想定することはできません。たとえ地主自身が契約更新に前向きであったとしても、借地人から一方的に建物の買取を請求される可能性に備え、そのための資金を準備しておく必要があります。これは、地主に対して、契約期間満了が近づくにつれて、建物の潜在的な市場価値と自身の財務状況を積極的に評価することを促す効果を持ちます。
第3章 価格の決定:「時価」の多角的分析

本章では、最も紛争が生じやすい「価格」の問題を取り上げます。法律は「時価」での買取を義務付けていますが、この「時価」を定義することは複雑です。
3.1 基本的な算定式:建物価格+場所的利益
最高裁判所の判例は、「時価」が単なる建物の資材価値ではないことを確立しています。時価は、以下の2つの要素の合計であるとされています 。
- 客観的な建物自体の価格:建物の構造、経過年数、保存状態、そしてその建物を現時点で再建築した場合の費用(再調達価格)などを考慮して算出される物理的な価値です 。
- 場所的利益:その建物が、その特定の場所に存在すること自体によって生じる付加価値です 。
3.2 「場所的利益」の深掘り
- 概念:これは、建物の所有者がその立地(例:駅に近い、日当たりが良い、商業的な可能性があるなど)から享受する「事実上の利益」を金銭的に評価する、判例上確立された概念です 。これは借地権価格そのものではありませんが、密接に関連しています 。
- 実務上の評価:統一された算定式は存在しません。過去の裁判例を見ると、土地の更地価格に対する一定の割合として計算されることが多く、その割合は10%から30%と、事案によって大きく変動します 。
- 重要な判例:たとえ建物が老朽化し、物理的な価値がゼロ円と評価されたとしても、「場所的利益」が認められることで、相当額の買取価格が算定されることがあります。実際に、建物の市場価格がゼロであるにもかかわらず、場所的利益として土地価格の12%に相当する800万円の支払いを命じた東京地方裁判所の判例が存在します 。これは地主が理解しておくべき極めて重要な点です。
3.3 評価の基準時点
「時価」は、借地契約が満了した時点ではなく、借地人が建物買取請求権を行使した時点で決定されます 。これは、権利行使の瞬間に売買契約が成立するためです。
3.4 負担の存在が価格に与える影響
- 建物が第三者に賃貸されている場合:買取対象の建物がアパートなどで第三者に賃貸されている場合、地主は賃貸人としての地位を承継し、敷金の返還義務なども引き継ぐことになります 。そのため、買取価格は賃借権が付いた状態の収益物件としての価値で評価され、通常は低くなります。そして、未返還の敷金相当額は買取価格から控除されます 。もし敷金などの負担額が建物の価値を上回る場合、買取請求権自体が認められない可能性もあります 。
- 建物に抵当権が設定されている場合:建物に抵当権が設定されていても、買取価格からその債務額が控除されることはありません。地主は完全な時価を支払う義務を負います。ただし、民法の規定に基づき、地主は借地人が抵当権を抹消するまで、代金の支払いを拒むことができます 。
「場所的利益」という概念は、借地人に土地の所有権の一部を認めることなく、彼らがその土地で築き上げ、維持してきた価値の一部を間接的に補償するための、洗練された法的メカニズムと言えます。
契約が更新されないことで、借地権という土地を占有する法的権利は消滅します 。しかし、法律は、借地人の長期にわたる存在と建物の維持が、その場所全体の効用や価値に貢献しているという事実を認識しています。そして、その建物を単に取り壊すことは、その効用を破壊する行為だと考えているのです 。
最高裁判所は、「場所的利益」を「借地権価格」とは明確に区別しています 。これは微細ですが決定的な違いです。これにより、「影の価値」とも言うべきものが生まれます。借地人は失われた借地権そのものの対価を得るわけではありませんが、もはや占有する権利を持たない土地と不可分に結びついた、建物の 状況的な価値について補償を受けるのです。
これは、法が示した現実的な妥協点です。借地人が何も得られずに立ち去ることも、地主が(借地人が建設し、本来なら解体費用を負担するはずだった建物を失った)更地を手に入れて棚ぼた的な利益を得ることも防ぎます。根本的な法的権利が消滅した後でも、当事者間の現実的な状況を反映した金銭的解決を強制する、非常に実用的な制度なのです。
第4章 権利が適用されない場合:重大な例外と除外事由
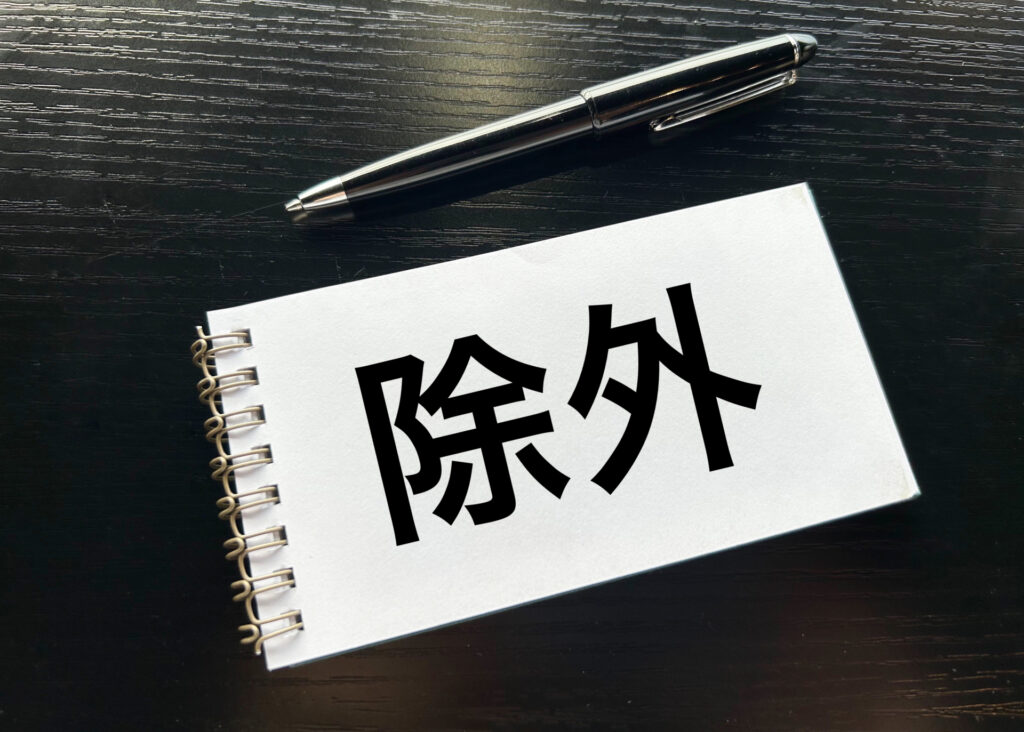
本章は、借地人にとって極めて重要な警告です。この強力な権利は絶対的なものではなく、特定の状況下では失われる可能性があります。
4.1 最も重大な失権事由:借地人の債務不履行
借地契約が、借地人の契約違反を理由に地主から解除された場合、建物買取請求権は完全に失われます。これは最も一般的かつ深刻な例外事由です 。
債務不履行の典型例は以下の通りです。
- 地代の慢性的な滞納
- 地主の承諾を得ない土地の転貸や借地権の譲渡(無断譲渡・転貸)
- 地主の承諾を得ない建物の増改築(無断増改築)
- 契約内容に反する目的での土地利用
この背景にある法的論理は、建物買取請求権が誠実な借地人を保護するための制度であるという点にあります。地主との信頼関係を破壊した借地人は、この特別な法的保護を受けるに値しないと判断されるのです 。
4.2 合意解除の効果
地主と借地人が双方の合意によって借地契約を終了させた場合(合意解除)、建物買取請求権は自動的には発生しません。合意に至る過程で、借地人はこの権利を放棄したものと推定されます。ただし、合意解除の契約書の中で、建物の買取を条件とすることが明確に定められていれば、その合意が優先されます 。
4.3 現代的な例外:定期借地権
1992年の借地借家法改正で導入された、更新を前提としない「定期借地権」では、ルールが異なります 。
- 一般定期借地権:契約時の特約によって、建物買取請求権を排除することが可能です。そして実務上は、ほぼ全ての契約で排除されています。この場合、借地人は契約終了時に建物を自費で解体し、更地にして土地を返還する義務を負います 。
- 事業用定期借地権:建物買取請求権は法律上、当然に排除されています。この権利は適用されません 。
4.4 その他の除外事由
- 一時使用目的の借地権:建設現場の事務所など、明らかに一時的な使用を目的とした借地契約には、この権利は適用されません 。
- 使用貸借:土地を無償で借りている場合(賃貸借ではなく「使用貸借」)、借地権そのものが存在しないため、建物買取請求権も発生しません 。
表1:建物買取請求権の適用可否
| 契約終了の状況 | 建物買取請求権の適用 | 主な根拠 / 参照情報 |
| 普通借地契約の期間満了 & 地主が正当事由をもって更新拒絶 | 可 | 最も典型的なケース。権利が借地人の金銭的セーフティネットとして機能する。 |
| 普通借地契約の期間満了 & 借地人が更新を請求しない | 可 | 借地人は契約継続ではなく、資産の清算を選択できる。 |
| 借地人の地代滞納による契約解除(債務不履行) | 不可 | 「不誠実な」借地人と見なされ、法の特別な保護を失う。 |
| 借地人の無断転貸による契約解除(債務不履行) | 不可 | 信頼関係の破壊により、権利は失われる。 |
| 当事者間の合意による契約解除(合意解除) | 不可(ただし、買取の合意があれば別) | 合意の過程で権利を放棄したと推定される。 |
| 一般定期借地権(買取請求権排除の特約あり) | 不可 | 契約が有効に権利を排除しており、建物解体が義務となる。 |
| 事業用定期借地権 | 不可 | 法律そのものがこの種の借地権から権利を排除している。 |
第5章 権利行使のプロセス:請求から引渡しまで

5.1 権利行使のステップ・バイ・ステップ
- 要件の確認:借地人は、第2章で述べた4つの要件がすべて満たされていることを確認します。
- 正式な通知:借地人は、建物買取請求権を行使する旨を明確に記載した書面を、内容証明郵便などを利用して地主に送付します 。
- 売買契約の自動成立:地主がその通知を受領した瞬間に、法的に売買契約が成立します。この時点で、建物の所有権は法的に地主に移転します 。
5.2 法的な膠着状態:同時履行の抗弁権
契約が成立すると、双方に義務が発生します。法律は「同時履行の抗弁権(民法533条)」という原則を通じて、両当事者を保護します 。
- 借地人の権利:借地人は、地主が買取代金を支払うまで、建物の明渡しや所有権移転登記手続きを拒否することができます。これは「留置権」によっても担保されます 。
- 地主の権利:地主は、借地人が建物の引渡しと登記書類の提供を申し出るまで、買取代金の支払いを拒否することができます 。
この同時履行の原則は、協力に向けた強力なインセンティブを生み出します。一方の当事者が義務を履行したにもかかわらず、他方が履行しないという事態を防ぐためのものです。これにより、当事者は取引を完了させるために、最後の争点である「価格」を解決せざるを得なくなります。
権利が行使され、所有権が瞬時に移転するという法的効果 は、地主を「まだ代金を支払っていない建物を所有している」という状況に置きます。一方で、借地人は「もはや自分のものではない建物を占有している」状態になります。
ここに同時履行の原則 が介入し、法的な「ロック」状態を作り出します。借地人は代金が支払われるまで立ち退きを強制されず、地主は建物の引渡しを受けなければ代金を支払う必要がありません。この法的な膠着状態は、もし当事者が最後の変数である価格について合意できなければ、両者が身動きが取れなくなることを意味します。
この仕組みは、必然的に当事者を価格交渉、あるいは最終的には訴訟へと向かわせます。それが、この膠着状態を打開するための最後の鍵となるのです。なお、この膠着状態の間、借地人は土地の使用を継続しているため、一般的にはその対価として賃料相当額を地主に支払う義務を負うと解されています 。
第6章 紛争と膠着状態の打開策
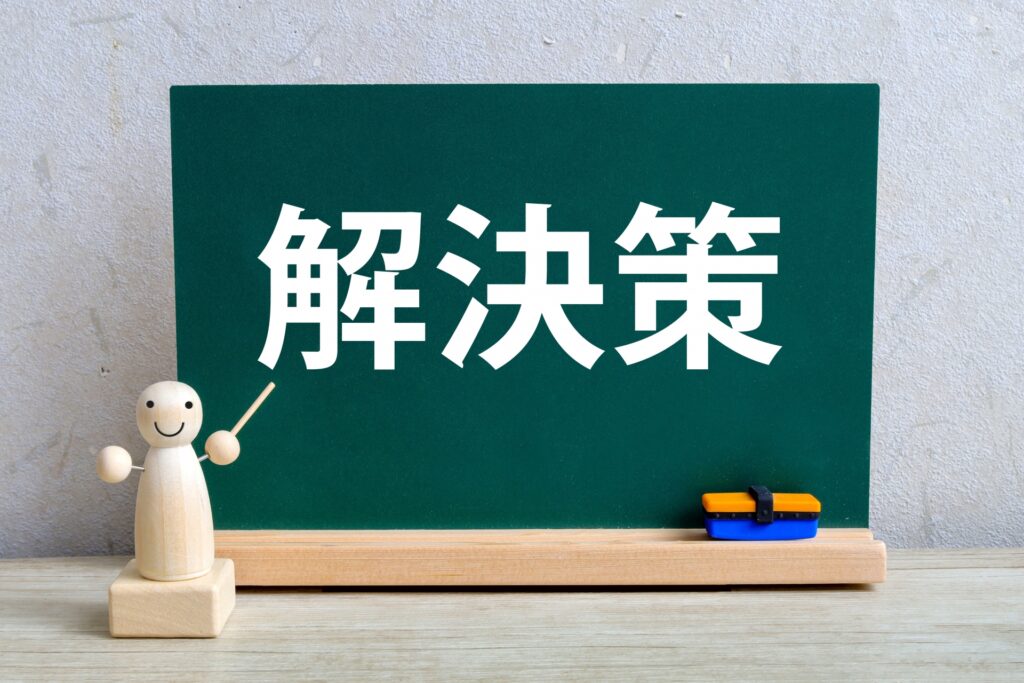
6.1 最大の火種:価格交渉
最も一般的な紛争は、「時価」、特に「場所的利益」の評価をめぐって発生します 。
- 最善の実務:両当事者は、それぞれ独立した不動産鑑定士から鑑定評価書を取得することを検討すべきです。鑑定評価に法的な拘束力はありませんが、専門家による客観的な評価は交渉の土台となり、裁判になった場合には極めて有力な証拠となります 。
6.2 地主が支払いを拒否した場合
地主が権利の存在は認めつつも、合意した、あるいは裁判所が決定した価格の支払いを拒否する場合、借地人の対抗策は、売買代金の支払いを求める訴訟を提起することです。借地人は、判決に基づく支払いが完了するまで、同時履行の抗弁権を根拠に建物の占有を継続することができます 。
6.3 代替的紛争解決:借地非訟手続
建物買取請求権そのものは、通常、借地非訟という簡易な裁判手続の対象とはなりませんが、関連する紛争で利用されることがあります。例えば、契約期間満了前に、借地人が借地権を第三者に売却しようとした際に地主が承諾しない場合、借地人はこの手続を利用して、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます 。この関連手続を理解しておくことは、借地人が自身の選択肢を広く検討する上で有益です。
6.4 地主と借地人への提言
- 借地人へ:地代の滞納は絶対に避けてください。全てのやり取りを記録に残し、契約満了前に専門家(弁護士)に相談してください。あなたの最強の権利は、あなたが契約を誠実に履行していることが大前提です。
- 地主へ:買取請求を安易に拒否できると考えないでください。この潜在的な債務に対して、事前に資金計画を立てておくことが賢明です。もし契約終了を望むのであれば、明確な「正当事由」を準備し、建物の価格交渉に応じる覚悟が必要です。早期に専門家を関与させましょう。
結論:円滑な移行のための要点

- 借地人への要約:建物買取請求権は、あなたが誠実な借地人であった場合にのみ機能する、強力な金銭的セーフティネットです。これにより、投下資本を回収することが可能になります。自身の権利を知ると同時に、義務も深く理解してください。
- 地主への要約:普通借地契約において、これは拒否することも契約で排除することもできない、回避不能な義務です。重要なのは、「場所的利益」を含む価格算定のプロセスを理解し、金銭的な準備を怠らないことです。
- 最終的な提言:借地契約の終了は、法律上も財務上も複雑なイベントです。地主、借地人双方にとって、契約期間満了日よりもかなり早い段階で、借地借家法に精通した弁護士と、資格を持つ不動産鑑定士に相談することが強く推奨されます。費用と時間のかかる訴訟よりも、事前の情報収集に基づいた、誠実な交渉が常に望ましい解決策です。


